郷原信郎著『”歪んだ法”に壊される日本』を読む
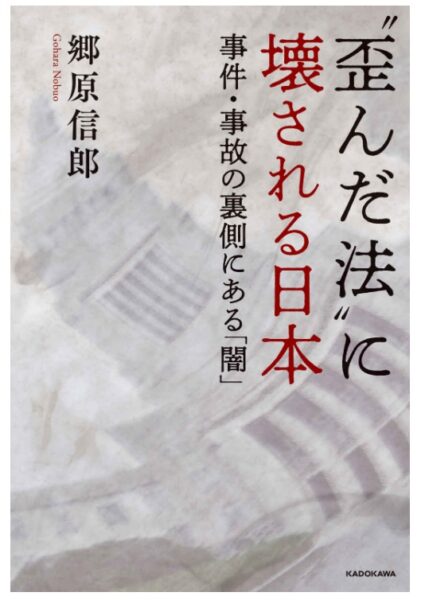
再審が決まった「袴田事件」は、乱暴な捜査が許された遠い昔の冤罪事件のように思っていました。しかし、郷原伸郎さんの近著『“歪んだ法”に壊される日本 事件・事故の裏側にある「闇」』(KADOKAWA)を読むと、袴田事件のような冤罪事件は今も起きているし、今後も起き続ける、という思いになりました。
郷原さんは、検事から弁護士になり、コンプライアンスの視点から社会を見てきた人で、本書では、自らが弁護士としてかかわった事件を含め、日本の法制度や法意識をめぐる問題をさまざまな事例や視点から提起しています。(下の写真は、郷原総合コンプライアンス法律事務所のHPに掲載された郷原信郎氏の写真)

本書の第1章「刑事司法が『普通の市民』に牙をむくとき」は、東日本大震災緊急保証制度を悪用したとして実刑判決が確定した経営コンサルタント、30万円の収賄事件で逮捕された全国最年少の市長、取引先企業の脱税をほう助したとして長期の拘留のすえ実刑判決を受けた実業家などの事例が記述されています。いずれも司法当局による強引な見立てや捜査、拘留の実態がよくわかります。
司法当局がいったん犯罪の見立てをすると、その筋書きに沿って捜査を進め、容疑者を逮捕すると、無実を主張しても長期間の拘留の末、保釈をエサに“自白”を強いる。やっと保釈されても、裁判では、”自白“した調書や上申書が証拠になって、実刑判決が下される。まるで犯罪ドラマのような「人質司法」が日本では当たり前のように行われているというのは、「普通の市民」にとっても、空恐ろしいことだと思いました。
もちろん、司法当局の見立てが刑事ドラマのように事実であることもあるのでしょうが、見立て違いだった場合、「普通の市民」は犯罪者の烙印を押され、それまでの「普通の市民」としての生活を奪われることになります。それを見極めるのが裁判所の役目ですが、「疑わしきは罰せず」(疑わしきは被告人の有利に)という原則が日本では十分に貫かれているようには思えません。
本書には取り上げられていませんが、袴田事件では、殺人事件の犯人とされた袴田巌さんの45通の自白調書のうち、静岡地裁が証拠として採用したのは1通だけで残りは無効とされました。自白調書への97%の疑わしさも、被告には有利に働かなかったことになります。犯行を裏付ける着衣が当初のパジャマから公判の途中で「発見」された別の着衣に変更されたことについても、死刑判決が確定されるまでの過程で、裁判所は「疑わしきは無罪」とする合理的な疑いを持ちませんでした。
第2章「『日本の政治』がダメな本当の理由」は、2019年の参院選をめぐる河井克行・案里夫妻の大規模買収事件、アキタフーズが元農水相に渡した「ヤミ献金」、安倍首相の「桜を見る会」前夜祭の費用問題などを取り上げ、政治資金や選挙資金を規制する法律が不透明であったり、抜け道の多い「ザル法」になったりしていることを示しています。
政治にかかわる法律は、どうせ政治家の都合のいいようなものになっているのだろう、というあきらめが私たちにはあります。しかし、本書は、法律の問題点を具体的に指摘するとともに、どうすればよいのかという改善策についても、条文改正案を示すなど、政治家が信頼される存在となる道を示しています。
政治とカネにかかわる法律がザル法になるのは、議員立法で決められているからだと、そのからくりを説明したうえで、著者は次のように提言しています。説得力のある提言なので引用します。
「国会議員に、自分達を律する法律の制定改廃を委ねるのは利益相反そのものであり、適切な立法が期待できないのは当然である。公正・中立な検討機関を設置し、その提言を尊重して立法を行う義務付けをするなど、政治に関する立法のルールを抜本的に改めなければ、日本の政治が健全になることは期待できない」
第3章「東電旧経営陣への13兆円賠償命令という『異常な判決』」は、電力会社のガバナンスの不在、第4章「『消費税は預かり金』という“虚構”が日本経済を蝕んでいる」は、消費税が取引の各段階に課せられる付加価値税なのに、消費者が負担する「預り金」というフィクションを広めた結果、小規模な事業者に対する「益税」とか「預り金泥棒」といった不当な非難が起きていることなどがわかりやすく解説されています。
第5章「交通事故の加害者が“つくり出される”とき」は、第1章と同じように衝撃的でした。それは、「運転手の操作ミス」とされる交通事故に、「車両の不具合」という可能性はないのかという問題提起とともに、2016年に起きた軽井沢バス転落事故が例示されていたからです。
このニュースをちゃんとフォローしていなかったためですが、私の頭のなかでは、運転手が坂道を下るのにエンジンブレーキを使わずに、フットブレーキばかりを使っていたため、ブレーキが焼き切れて、カーブでも速度を落とすことができなかった事故だと思っていました。
本書を読むと、事故原因は運転手がブレーキを使い過ぎたからではなく、使わなかったからということになったようです。司法当局も事故調査委員会(交通事故総合分析センターの組織)も、運転手はブレーキも使わずに、時速90キロを超えるスピードで走行したためカーブを曲がり切れなかった、と判断しているのです。
しかし、著者は、危険を察知すればどんな運転手もブレーキを踏むはずで、「警察のストーリーは、運転手の行動としてあり得ないように思える」と記しています。もし、運転操作の誤りでないとすれば、もうひとつの原因は車両の不具合となりますが、事故調査委はその可能性を否定しています。それなら、やはり操作ミスかとなるのですが、本書は重要な指摘をしています。それは、事故車両が検証のために持ち込まれたのが事故車両を製造したメーカー系列の整備工場だったことです。もし、整備工場の職員が検証に何らかの形でかかわっているのなら、「ブレーキの不具合等の車体の問題の有無について、原因究明の客観性が阻害されている」という本書の指摘は当然だと思います。
私も事故調査報告書を読んでみましたが、ブレーキの空気圧が低下した場合に鳴る警告音を乗客に聞いた記憶がない、ブレーキ用のエアタンクからの水分の流出はない(つまり、事故時に水分が入り凍結していた可能性はない)などの記述があり、ブレーキ系の不具合の可能性についても検証しているようです。しかし、運転手の勤務状況などの詳細の記述に比較すると、車の不具合についての検証の記述は少ない印象を持ちました。
本書の意図は、事故原因の究明というよりも、捜査の基本である検証が事故車両のメーカー系列で行われていることへの疑問ですので、読者のひとりある私がこの事故について踏み込んで書くことはできません。しかし、著者の疑問と問題提起は共有しながら、今後の展開を見ていきたいと思いました。
終章「社会を覆う“歪んだ法”をなくしていくため」は、法教育の重要性が説かれています。言葉の上ではだいぶ社会に浸透してきた「コンプライアンス」や「ガバナンス」ですが、こうした規範を社会に根付かせていくには、学校教育の段階から、しっかりとした法教育が必要なのだとあらためて思いました。
本書全体を振り返って、新聞記者だった私の経験からの感想を加えるとすれば、日本の司法制度や運用のゆがみを放置してきた責任の一端はメディアにあるということです。日本は拷問等禁止条約の批准国として国連の拷問禁止委員会から繰り返し、代用監獄の廃止や取り調べにおける弁護人の立ち会いなどを求められています。この点では、日本は民主主義国の劣等生です。それなのに、この問題をメディはどれだけ真剣に取り上げてきたでしょうか。
なぜ、メディアが消極的なのかといえば、司法当局がいやがるようなことを書きたくないからです。社会的な弱者に寄り添って、権力をチェックするというのはメディアの大きな役割です。新聞社でいえば、「政治家と癒着する政治部」、「企業べったりの経済部」に対して「正義を振りかざす社会部」というイメージがあります。実際に政治家や企業の不正を暴くのは社会部が多いのですが、司法にかかわる問題になると、社会部も腰砕けのように思えます。それは、どこの警察や検察にも記者クラブがあり、警視庁や検察庁のような大きな組織に張り付いているのが社会部だからです。かれらは警察官や検察官との親密な関係のなかで、特ダネ競争をしているので、刑事司法の在り方などについて疑問を呈するような記事を書くことにはためらいがあるのです。
私も駆け出しの記者のときに、事件取材の特ダネは、なんといっても大きな事件で「きょう逮捕」を抜くことだと教わってきました。そのために捜査関係者の自宅を訪ねる「夜討ち」(夜回り)や「朝駆け」(朝回り)が必要だといわれ、私も一升瓶をぶらさげて、「サツカン」(警察官)の自宅を訪ねました。
経済部に移ってからも、企業の幹部や経済官庁の役人の家に夜回りや朝回りをするのは常態化していました。政治部の記者も社会部の記者も同じような取材をしていました。だから、経済部や政治部が取材先との緊密な関係をつくっているように、社会部も司法当局との緊密な関係をつくろうとしているわけで、事件取材で、司法当局の見立てに疑問を挟むような記事を書けば、その関係が崩れ、特ダネはおろか特オチになるリスクをかかえることになります。
事件取材で、司法当局への「夜討ち」「朝駆け」を含めた取材時間を、たとえば容疑者の弁護士への取材時間と比べれば、何十倍、何百倍にもなると思います。袴田事件など「冤罪事件」として取り上げられた事件取材でも、捜査段階で、弁護士の視点などを含めて警察の捜査を客観視する記事がどれだけ書かれたのか、検証に耐えるメディアがあるとは思えません。
私は1973年から1976年まで静岡支局に勤務していました。1966年に起きた「袴田事件」で、静岡地裁が1968年に袴田さんに死刑判決を下したあと、東京高裁が控訴を棄却するのが1976年ですから、そのころに静岡にいたわけです。しかし、警察担当ではなかったこともあり、裁判の記憶はほとんどありません。
私が覚えているのは、「島田事件」で、静岡県島田市で1954年に起きた幼児殺人事件で逮捕され、死刑判決が確定していた赤堀政夫さんが無実を訴え、何度かの再審を請求していた時期でした。なぜ島田事件の記憶が残っているのかといえば、当時、他社の記者だった人が「赤堀さんを救う」と言って会社を辞めたからです。記者が職を投げうって無実を訴えるほど、ひどい事件という印象があったのです。島田事件は、東京高裁が1987年に再審を決定し、差し戻された静岡地裁は1989年に無罪判決を下し、これが確定しました。
島田事件と袴田事件という冤罪が疑われる大きな事件にかかわる地域で、私は記者として勤務していたのですが、支局内で事件を検証しようという話が出た記憶はありませんし、私にもその問題意識はありませんでした。司法をチェックできないメディアを批判すれば、その矢は私にも飛んできます。
弁護士が立ち会わない「自白」に、証拠としての信頼性はない。その国の人権意識を測るうえで重要なこの物差しで、日本が合格するのはいつの日なのでしょうか。それには、警視庁クラブや検察庁クラブの「解体」が先決かもしれません。そんなことを考えながら、本書を閉じました。
| 前の記事へ | 次の記事へ |



コメントする