「トランプ革命」を考える①経済

米国のトランプ大統領が2期目の大統領に就任した2025年1月から、米国も世界も日本も大きな変化に直面している。コロンビア大学名誉教授のジェラルド・カーチス氏は、2025年5月に日本記者クラブで会見したときに、トランプ氏は米国と世界を根っこから変えようとしている「革命者」だとして、「米国版の文化大革命(文革)」だと語っていた。主義主張は別にして、これまでの政治、経済、文化の秩序を根底から覆そうという雰囲気は、1960年代後半から1970年代にかけて中国で起きた「文化大革命」と似ているのだろう。
そう考えると、MAGA(Make America Great Again)の赤い帽子をかぶった熱烈なトランプ支持者の姿は、文化大革命時に赤表紙の『毛沢東語録』を手に「造反有理」を叫んでいた紅衛兵の映像と重なって見えてくる。
「トランプ革命」とは何なのか、そして、米国にどう向き合うべきなのか、経済や安全保障、民主主義などの視点から考えてみたい。最初は、トランプ関税にまつわる経済の話からだ。
1 トランプ関税
就任前から「最も美しい言葉は関税」と語り、自らを「タリフマン」(Tariff Man=関税男)と称したトランプ大統領は、すべての輸入品を対象にした10%の一律関税、それに上乗せする相互関税、鉄・アルミ・自動車などに対する品目別関税、中国やカナダ、メキシコなど特定の国を対象にした関税を次々に発動している。
日本については、当初25%の関税を設定していたが、日米交渉の結果、自動車関税を含め15%とすることで、2025年7月に「決着」した。関税を引き下げる見返りに日本は5500億ドルを米国に投資することを約束した。しかし、日米合意の中身はあいまいなところも多く、米国が日本の約束違反を理由に、制裁的な関税を追加する余地は残されている。(写真は、トランプ氏と交渉する赤沢経済再生担当相=米ホワイトハウスの「ギャラリー」から)

日米間では、1986年に結ばれた日米半導体協定に日本が違反したとして1987年に米国が日本製のPCやカラーテレビなどに100%の制裁関税をかけた歴史がある。
日本との合意に倣うように、EUも2025年7月末に、自動車を含め関税率を15%とし、EUが6000億ドルの対米投資をすることなどで米国に米国と合意した。合意には、EUが米国から7500億ドル相当のエネルギーを3年間で買うことも含まれた。
トランプ関税の狙いは、自国の産業を守り貿易赤字を減らすという通商政策、減税に使うために関税収入をふやすという財政政策、移民や麻薬などの問題で相手国に対応策を迫る取引(ディール)のカードなどとみられている。
しかし、関税の引き上げによる自国優先主義が貿易全体を縮小させ、自国にも跳ね返ってくることは、1930年に発動された米国の「スムート・ホーレイ関税法」が国際的な関税の引き上げ戦争を招いたうえ世界をブロック経済化させ、第2次世界大戦の遠因になったことで証明されている。
大戦後の1947年に発効したGATT(関税及び貿易に関する一般協定)や、それを発展させた1995年発効のWTO(世界貿易機関)は、関税戦争の反省から自由貿易を広げるための協議や交渉、調停を進めてきた。トランプ関税は、こうした国際間の歴史的な努力を覆すものといえる。
「比較優位」への挑戦
トランプ関税は、自国のエゴをむき出しにした国際的な協調への挑戦であるだけでなく、デヴィッド・リカード(1772~1823)以来の経済学の基本ともいえる「比較優位」への挑戦でもある。
異なる国が商品を生産するときに、それぞれが相対的に効率的に生産できる商品に特化して、貿易で補ったほうがそれぞれにとっての利益が大きい。これがリカードの唱えた比較優位の経済原理で、それぞれの国が自国の比較優位な産業に特化するだけではなく、先進国が途上国に技術や生産を譲りながら、より高度な産業に集中していく歴史的な発展の展開としても考えられてきた。
この原理に従えば、現在の米国は鉄鋼や自動車、繊維製品、生活用品などの産業を外国にまかせて、半導体や医薬品など高度な技術や研究開発力のある分野に注力したほうが経済的な効率性が高いということになる。トランプ関税は、これに反して、鉄鋼や自動車などの比較劣位の産業を復活させようというのだから、経済的には非効率な資源配分となり、長期的には経済を衰退させることになりかねない。この論点から、多くの経済学者はトランプ関税を批判しているが、製造業の回復は雇用を増加に直結することから、自由貿易のもとで日陰者だった保護主義に光を当てることにもなっている。
日本の戦後復興と日米貿易摩擦
日本の戦後復興を振り返ると、戦後まもなくは、木製オルゴールやクリスマス雑貨、女性用ブラウスなどを米国に輸出して外貨を稼いだ。日本製のブラウスは「ワンダラーブラウス」(One Dollar Blouse)と呼ばれ、1950年代の半ばには、米国の繊維業界から日本の輸出制限を求める声が起こり、その後の日米貿易摩擦の発端となった。日本が綿製品の輸出を自主規制する日米綿製品協定が結ばれたのは1957年だった。
沖縄返還が決まったのは1969年の佐藤栄作首相(1901~1975、首相の任期は1964~1972)とリチャード・ニクソン大統領(1913~1994、共和党、大統領の任期は1969~1974)との首脳会談だったが、米国が返還に応じた裏には、日本が繊維製品の輸出自主規制をするという密約があったことが後に明らかになっている。このため、沖縄返還は「糸と縄との取引」と言われるようになった。
米国が沖縄という領土を譲っても繊維製品の貿易制限にこだわったのは、当時の米国にとって繊維産業の比重が重かったからだ。ニクソン氏は繊維製品の輸入制限を大統領選の公約にしていた。
しかし、米国の繊維産業は、日本に脅かされたのちも、東南アジアや中国、さらには南米との競争に敗れ、ラルフローレン、GAP、バナナリパブリックなどのファッションブランドは、その製品を途上国で生産することで生き残っている。製糸、紡績、縫製など繊維産業の工場が集約していたのがサウスカロライナ州だが、現在は、自動車(BMW、ボルボ)、航空宇宙(ボーイング)、生命化学(ジョンソン&ジョンソン)などのハイテク産業、アグリビジネスの拠点になっている。もはや綿ぼこりの繊維工場で働こうという労働者は少なくなった。
日米間の貿易摩擦は1970年代に入ると、造船、鉄鋼製品などの重工業製品で広がり、1980年代に入ると、テレビなどの電気製品(エレクトロニクス)、自動車、工作機械、半導体など製造業全体に及ぶようになった。こうした分野で日本が比較優位に立ったということで、貿易摩擦は激しさを増すことになった。米国は、日米構造協議などを通じて日本の輸出志向を内需に向けさせる一方、金融、情報技術(IT)などの新しい分野での巻き返しをはかった。
1990年代後半に入ると、米国はこうした分野の技術発展と成長が著しく、製造業で日本や西独(現ドイツ)に敗れたのが見事に復活した。日本が1980年代の後半から1990年代の前半にかけて、バブル景気に酔っていた時期、米国ではカリフォルニアのシリコンバレーを中心に、新しい企業がアイデアと技術で産声をあげていたことになる。
もし、米国が保護主義にこだわり、高関税などの貿易措置で、エレクトロニクスや自動車などの製造業を守ることに専念していたら、第3次産業革命と呼ばれる情報技術革命の波に乗り遅れていただろう。
トランプ大統領の頭の中は1980年代
「日本は米国で何百万台もの車を売っているのに、我々は車を日本で売っていない。日本が米国車を受け入れないからだ」(2025年7月14日、記者団との問答でのトランプ大統領の発言、写真は、自動車への関税に署名したトランプ大統領=米ホワイトハウスの「ギャラリー」から)

トランプ大統領の通商政策をめぐる発言をみると、1980年代に戻ったような錯覚に陥る。当時、燃費が良く故障の少ない日本車は米国市場で人気を集め、米国の自動車メーカーの経営を圧迫することになったため、日本は1981年に米国での自動車販売を168万台とする自主規制を始めた。自由貿易を掲げる米国は貿易制限などの措置で自らの手を汚さず、日本に自主規制という対応を迫った背景がある。その後、日本のメーカーが米国内に生産工場をつくるようになったことから1994年に自主規制は撤廃された。
一方、日本市場をみると、米国車の販売台数は少なかったが、日本は1979年に自動車の関税をゼロにしていたので、米国が批判したのは、日本独自の安全規制やメーカー系列のディーラー中心の販売網のあり方だった。
日本は、米国の批判をかわすために、国際的な安全基準を設定するようになった。しかし、米国は独自の安全基準を設けているため、米国通商代表部(USTR)が毎年、公表している「外国貿易障壁報告書(NTE)」では、日本が米国の安全基準基準を認めていないのは「非関税障壁」だと批判している。
販売網については、メーカー系列のディーラーが販売するという日本の販売システムにあわせて、メルセデス・ベンツ、BMW、フォルクスワーゲン、アウディ、MINIなど欧州のメーカーは、それぞれ日本に販売法人を設立し、ディーラー網を整えた。
日本で米国車の販売数が伸びないのは、大きな車体と大きなエンジンという「アメ車」の魅力が日本市場では、生かされないからだろう。いま、日本でもっとも売れている米国車はJeep(メーカーはステランティスという多国籍企業)だが、搭載しているエンジンは、日本市場に合わせて排気量の小さいものが多い。
1980年代の後半に、USTRで通商代表補代理などを勤めたグレン・フクシマ氏は朝日新聞のインタビュー(2025年5月31日)で、「トランプ氏の日本に対する見方は、1980年代からほとんど固まったまま」としたうえで、その中身を次にように語っている。
「トランプ氏からみれば、第2次世界大戦直後、米国の世界的な地位が相対的に低下した最大の理由は、日本などが米国を『食い物にしてきた』からです。日本は米国をだまし、物を売って金もうけをしてきた。米国からは物を買わず、円を操作して、(安全保障を米国に)ただ乗りしている、とみてきました」
トランプ氏にとって貿易問題の原風景は1980年代ということになる。当時のトランプ氏は、不動産ビジネスの風雲児として名を馳せていた。1976年に父が設立した不動産会社を引き継いだトランプ氏は、ニューヨークのマンハッタンに進出し、大型ビルの買収や建設を手掛け、1983年にはトランプタワーを建設、1988年にはニューヨークを象徴するプラザホテルを買収した。
当時の日本は、1989年に三菱自所がニューヨークのロックフェラービルを買収するなど米国での不動産投資を強めていた。トランプ氏にとって、日本は不正な貿易で稼いだ金でニューオークを買いあさっている競争相手と映っていたのだろう。
私がトランプという人物を意識したのは、1989年に彼がイースタン航空を買収して、ニューヨーク・ワシントンを往復する「トランプ・シャトル」を運航し始めたときだった。ワシントン駐在でニューヨークとの往来にシャトル便を頻繁に利用していたので、トランプとはどんな人物なのか調べたら、不動産ビジネスの成功者だとわかり、うさん臭い経営者という印象を持った。
その後、1991年にはアトランティックシティに豪華なカジノの施設を建設したものの、資金繰りが悪化し、最終的には2004年に破産に追い込まれた。トランプ航空も赤字続きで1992年には売却、プラザホテルも経営難から1995年には手放すことになった。濡れ手に粟のビジネスは失敗する、というのが私の印象だった。
ところが、いろいろなビジネスで失敗したトランプ氏は1990年代の後半になると、米国経済の復活を背景に不動産ビジネスでよみがえりました。2004年からは、テレビの「アプレンティス」というリアリティ番組の司会者として人気を得るようになり、この番組は2015年まで続きます。政治的な野心も次第に膨らんだようで、2000年の大統領選挙では、改革党という政党の大統領候補として名乗りを上げ、パット・ブキャナン氏らと争い、早い段階で撤退した。しかし、2016年の大統領選では共和党の候補として名乗りを上げ、党内でトランプ旋風を巻き起こして共和党の大統領候補になると、そのままの勢いで、本番の大統領選でも民主党のヒラリー・クリントン候補を破り、大統領の座を獲得した。
2000年の大統領選のとき、私は2度目のワシントン駐在で選挙戦を取材した。選挙は共和党のジョージ・W・ブッシュ氏と民主党のアル・ゴア氏の争いが焦点で、投票後も混戦状況となり、最終的にはブッシュ氏が43代の大統領に就任した。トランプ氏は泡沫候補という記憶しか残っていない。
「悪いのはアメリカ」
トランプ関税という他国から見れば理不尽な要求に対して、日本は、対抗して米国製品に関税をかけることなく、赤沢亮正経済再生担当相が8度も訪米して交渉した結果、米国から譲歩を得ることができた。日本国内から、米国を批判する声は小さく、公的な発言で唯一ともいえる例外は、石破首相が参院選挙中の選挙演説で「これは国益をかけた戦いだ。なめられてたまるか」と発した言葉ぐらいだろう。
1980年代の日米貿易摩擦では、1987年4月に米国が日米半導体協定の不履行を理由に制先関税を課した直後、月刊誌「文藝春秋」は6月号で「悪いのはアメリカだ」と題した特集を組み、話題になった。また、1989年には、石原慎太郎と盛田昭夫が共著で出版した『「NO」と言える日本』(光文社)がベストセラーになり、米国でも英訳された文書が米議会でも回覧された。
当時、私はワシントンで、日米貿易摩擦を取材しながら、日本製品の優位性を認めていたものの、日本市場の閉鎖性については、米国の批判に頷くことが多かった。だから、「悪いのはアメリカ」といった反米感情の高まりには、不安を覚えていた。当時の日本国民は、自動車やパソコンなどで日本製品に負けた米国がくやしまぎれに「ジャパン・バッシング」をしている、という思いが強かったのだろう。まさに、「なめられてたまるか」という思いだ。
しかし、40年後のいま、日本国内から反米感情が高まっているように見えないのは、「トランプ相手では仕方がない」という冷静というか、あきらめに似た思いがあるからだろう。それとともに、もはや日本製品の優位性について、自信を失っていることもあるのではないか。『ジャパン・アズ・ナンバーワン』(1979年、エズラ・ヴォーゲル)と言われ、自信過剰になっていた時代だからこそ、「悪いのはアメリカ」と言えたのではないか。
2 保護主義は悪か
一般的な関税の主目的は、自国の産業保護だ。トランプ関税も自動車、鉄鋼など米国経済を支えてきた産業の復活を目的に掲げている。中西部を中心に多くの工場労働者を雇用してきたこれらの産業は、自動車では日本やドイツ、鉄鋼ではインドや中国などとの競争に敗れ、多くの工場が操業を止め、失業者も多く、ラストベルト(赤さび地帯)と呼ばれるようになった。大統領選でトランプ氏を支持したのはラストベルトの労働者や失業者で、トランプ氏も選挙公約通りに、関税によって外国からの工場投資を呼び込み、雇用をふやそうとしている。
経済学者の語る経済効率からいえば、自由貿易による国際分業のほうが効率的に決まっている。しかし、自動車や鉄鋼労働者がすぐにIT産業のソフトエンジニアに転職できるわけではない。政治家が中西部の「票田」で多くの票を獲得しようとすれば、高関税による製造業の復活を主張するのも無理なからぬとこころだ。日本でも自由貿易の例外として稲作を保護しているのは、与党も野党も地方の水田と票田に期待しているからだろう。
一国の経済効率性でみれば、衰退する製造業の「復活」はヒトやカネの最適な資源配分からはずれるので、好ましいことではない。しかし、地域経済という視点から見ると、製造業は多くの工場労働者を雇うので、雇用を安定させる力があり、それによって地域経済が潤うのも事実だ。
一国の指導者としては、地域の利害を代弁する議員とは異なるので、国民経済の視点で政策を打ち出す必要がある。そうなると、比較劣位の衰退産業については、雇用も含めて別の産業への転換や移動を促進するための政策が必要で、どこの国でもそういう政策が実行されてきた。日本では、1950年代の最盛期に45万にのぼった炭鉱労働者をほかの産業に移動させる政策が行われた。
トランプ関税は、こうした経済政策の「常道」に反しているのは明らかだ。しかし、比較優位の原則に沿った国際分業は、国際的には「最適解」ではあっても、一国だけの利益を考えたときに、それが必ずマイナスになると言い切れるのだろうか、という疑問もある。
「近隣窮乏化」路線
「近隣窮乏化」という言葉がある。ある国が自国の経済状況を改善するために、貿易相手国の迷惑を考えずに、関税を引き上げたり、通貨を意図的に引き下げたりして、輸入を減らし輸出を増やす政策だ。近隣諸国が貿易相手国という意味なら、トランプ関税はまさに近隣窮乏化の政策だ。
トランプ関税の現状をみれば、輸入者が関税を負担するだけでなく、輸出者も関税の引き上げに応じて輸出価格を値引きしたり、生産を縮小したりしている。米国の消費者も関税の引き上げによる値上がりで、関税の一部を負担しているが、トランプ大統領が主張するように、増加する関税収入を減税などで国民に還元するなら、最終的には輸出する側だけが値引きや生産減少による損失を被ることになる。
米国第一主義からすれば、近隣諸国の窮乏は知ったことではないかもしれないが、長期的にみれば、貿易全体が縮小することは、どの国の経済も縮小させることになり、貿易の規制は、近隣諸国だけではなく自国にもマイナスになる。ただ、米国のように、エネルギー資源を含め、自給自足ができる国では、こうした政策のマイナス面はすぐに現れないかもしれない。
トランプ大統領は、鉄鋼やアルミニウムの関税は50%を維持するとしている。自動車など鉄材を使う産業にとっては、関税で高くなった外国製の鉄鋼を買うか、これまでは買う気がなかった国内産の鉄鋼を使うかの選択に迫られる。どちらにせよ、自動車メーカーにとってはメリットの少ない取引だが、自動車については25%(日本車は15%)関税で保護されているのだから、輸出を考えなければ、国内販売で利益を得ることはできるだろう。
大きな国内市場を持っているということは、国際的に優位とはいえない産業でも、しばらくは生き残れる可能性がある。外国企業も、米国市場での売り上げを期待するなら、米国内に生産拠点を移すことも考えるだろう。
米国一国主義を掲げるトランプ大統領は、トランプ関税の長期的なデメリットよりも短期的なメリットを直感的に感じているではないだろうか。
重商主義の米国
最初のトランプ政権が誕生したときに、貿易収支の赤字を悪、黒字を善とみなす通商政策を見ながら、これは現代の重商主義だと思った。収奪や貿易による「国富」の増大に力を入れ、植民地の拡大、保護主義の強化をはかったのが16世紀から18世紀の欧州の重商主義だった。
植民地の金や銀、プランテーションに支えられた重商主義は、一言で言えば「やらず、ぶったくり」だから、その背景には、大きな経済力や軍事力が控えていて、そうしたパワーを持った国が覇権国として国富を増やした。16世紀から18世紀にかけてのスペインやフランス、17世紀から18世紀にかけてのオランダ、19世紀以降の英国などだ。
しかし、南米の金や銀、アジアの香辛料の収奪で繁栄したスペインやオランダは、国内の手工業などが発展しないまま次第に衰退した。工業という新たな価値を増やすタネ酵母が不十分だったため、パイの奪い合いに終わってしまった。歴史上の重商主義は、それぞれが得意な産物を生産し、交換し合う自由貿易主義に優位性を奪われた。
トランプ政権をみると、関税政策による国内の産業保護に加えて、カナダの米国への編入やグリーンランドの領有、パナマ運河の獲得など「植民地」の獲得を目指しているようで、初期の重商主義に磨きをかけているように見える。
ビジネスも国家間の貿易も、「ぶったくり」(rip-off)の競争だと信じているトランプ氏の「本性」を見抜いたのがトランプ1.0に接したドイツの首相だったアンゲラ・メルケル氏だった。彼女の回想録『自由』(KADOKAWA)を読むと、2017年3月に、トランプ大統領との米独首脳会談を終えたメルケル氏は、トランプ氏について、次のような評価をしている。
「政界に入る前は不動産ビジネス界にいたトランプは、あらゆることを不動産事業家の視点から判断する。すべての土地は一度しか売りに出されない。自分が手に入れなければ、それは誰か他人のものになる。これが彼の世界観だった。トランプにとって、すべての国は互いに競争関係にあり、一方が勝てば、もう一方は負ける。協力することで全員がより豊かになれるとは、信じていないのだ」(『自由』下巻)
国際間の協調によるウィンウィンの関係を進めようとしたメルケル氏にとって、トランプ大統領の出現はやっかいな出来事だと思ったに違いない。メルケル氏の回想録はトランプ2.0の前に執筆されているが、トランプ2.0を見れば、彼女のコメントが正しかったと確信するだろう。
トランプが好むマッキンリー
トランプ大統領が就任して真っ先に実行した「政策」のひとつがアラスカ州にある北米大陸の最高峰デナリ(標高6190m)の名称をマッキンリーにしたことだ。先住民の間では、デナリと呼ばれていたこの山は1897年に、当時のウィリアム・マッキンリー大統領(1843~1901、共和党、大統領任期は1897~1901)にちなんで連邦法でマッキンリーになったが、周辺の国立公園がデナリであり、アラスカ州もデナリとするように求めていたことから2015年にオバマ大統領がデナリの名称に戻していた。(写真は、ウィリアム・マッキンリー大統領=ウィキペディア)

トランプ大統領にとって、マッキンリーがお気に入りの大統領になったのは、50%超の高関税(マッキンリー関税法)を成立させたことで、「タリフマン」と呼ばれたこととともに、1898年の米西戦争で勝利し、スペインからフィリピン、グアム、プエルトリコを戦利品として獲得、さらにハワイを併合したことで、米国が帝国主義になった時代を象徴する大統領だからだろう。
米国史のなかで米国の太平洋への帝国主義的な進出は、西部開拓が一段落し、1890年には「フロンティアの消滅」が言われたあと、さらに太平洋に出て西進するモティベーションとなったのが「明白なる使命」(Manifest Destiny)という言葉で正当化された。ただ、フィリピン併合は、米西戦争時にフィリピン独立派に戦後の独立を約束して裏切ったため、1889年から1902年にかけて米比戦争を招いた。
マッキンリー大統領が活躍した19世紀末の米国は、鉄道、製鉄、石油、電気などの新しい分野で、産業資本が巨大化する時期で、「泥棒貴族」と揶揄された資本家たちが豪華な生活を競い合い、「金メッキの時代」(Gilded Age)の輝きを放っていた。トランプ大統領は、就任演説で「米国の黄金時代がいま始まる」と宣言したが、黄金が関税という金メッキで輝くだけのフェイクであり、その金メッキも剥げ落ちるかもしれない。
トランプ大統領がマッキンリー大統領を持ち出したことは、米国民にとって意外だったようだ。民主党の大統領が尊敬する先達としてフランクリン・ルーズヴェルト大統領(1882~1945、民主党、大統領任期は1933~1945)を挙げるのに対して、共和党の大統領は、セオドア・ルーズヴェルト大統領(1858~1919、共和党、大統領任期は1901~1909)を挙げることが多かったからだ。「忘れられていた大統領をトランプが蘇らせた」といった評価も出てきた。
マッキンリー大統領は、1900年に再選されたものの1901年に銃撃によって暗殺された。大統領選の最中に銃撃を受けたトランプ氏は、マッキンリーと違って生き延びたことで使命感を感じたのかもしれない。
3 貿易収支と為替変動
トランプ大統領が貿易赤字は悪、黒字は善だと考えていることは、今回のトランプ関税で、貿易相手国別に示された関税率が貿易赤字の大きさから算定された数字だということからも明らかになった。国別の関税率は、それぞれの国に対する貿易赤字をゼロに近づけるのが狙いであるからだ。
しかし、貿易赤字は本当に悪なのだろうか。輸入するのは、その国の需要を充たす生産がないからで、米国はドルという紙切れで、米国民の需要を充たす商品を手に入れたことになる。米国が貿易赤字国に赤字の削減を迫ることは、自国の消費者に需要を減らすように求めていることになる。トヨタのレクサスを買い替えようと思っている人にとって、自動車関税がかかってもレクサスを買おうと考えるなら、ほかの消費を控えてレクサスを手に入れるだろうし、買い替えは難しいと考えれば、そのまま古いレクサスに乗り続けるかもしれない。レクサスへの需要が強く、シボレーへの買い替えが起きなければ、関税は経済を縮小させる方向に働く。
変動相場制の自動安定機能
変動相場制のもとで、ある国の貿易収支が赤字になると、その国の通貨の評価(為替相場)は下落し、そうなると輸出がしやすく輸入がしにくくなるので、貿易収支は改善し、通貨も上昇する。逆に、貿易収支が黒字なら、通貨は上昇し、輸出がしにくく輸入がしやすくなるので貿易黒字は減り、通貨も下落する。これが変動為替制度の持つ自動安定装置としての機能だ。
ところが、米国の場合、慢性的な貿易赤字なのに、ドルの価値はそれほど低下していない。その理由は、ドルが貿易決済や金融資産の通貨として使用されたり、保有されたりする「基軸通貨」であるため、ドルへの需要が強いからだと見られている。各国の政府や中央銀行が蓄えている外貨準備の約60%はドルという。貿易取引などの実需を超える資産としてのドル需要がドルの為替相場を押し上げていることは確かだろう。ただ、米国が慢性的な貿易赤字になった1980年代で、それまでは貿易黒字だったから、貿易赤字が必ずしも基軸通貨国のコストとはいえない。
基軸通貨国は、そのことによって通貨が過大評価されているかもしれないが、それは負担でもあり恩恵でもある。5万ドルでトヨタのレクサスを買っている米国民は、ドルが基軸通貨でなかったら、あと数千ドルも多く支払わなければならないかもしれないのだ。
米国は基軸通貨のコストをドル高による貿易赤字で支払っている、と主張したのがトランプ関税の推進者といわれるスティーブン・ミラン大統領経済諮問委員会(CEA)委員長だ。ミラン氏が委員長に就任前の2024年11月に発表した「国際貿易システム再構築のユーザーガイド」は、ドルが基軸通貨であるため高く評価され過ぎているのを是正するには、多国間の合意でドル安に誘導する必要があるとして、マール・ア・ラーゴ合意」を提案した。通貨の価値は為替市場で決まるが、基軸通貨であるがために高くなっているのなら、そのプレミアム分は国際的な合意で下げるべきだというのだろう。
為替についての合意は、主要5か国(米、英、仏、西独、日本)の財務相が1985年9月、ニューヨークのプラザホテルに集まり、ドルの引き下げを決めた「プラザ合意」を想定しているようだ。しかし、世界経済や世界貿易に占める米国の比率はプラザ合意の時代よりも大幅に低下しているし、中国やインドなど新たな国際貿易のプレイヤーも力をつけている。ユーロ圏も20か国あり、ユーロの切り上げを議論するだけでも大騒ぎになるだろう。国際間の通貨合意で、為替市場の領域に国家が介入することは、まず不可能だ。
国際的な合意が難しいとなると、米国が関税を交渉のカードに使って、個別に為替相場を誘導することはあるかもしれない。たとえば日本に対して、円高にするための利上げを要求する、といったことだ。
関税収入で減税
トランプ大統領は、関税収入を減税の財源に充てるという。米国の2024年の輸入総額は3兆2,535億ドルだから、仮にすべての輸入から15%の関税を得られるとすると、関税収入は4,880億ドルとなる。トランプ氏が「ひとつの大きく美しい法案」と名付けて成立させた法案に盛り込まれた減税規模は、10年間で6兆ドルを超えるとみられ、年間では6000億ドル超だから、この通りの関税収入が得られれば、関税輸入である程度の減税を賄えることになる。
米財務省によると、今年1月から6月までの関税収入は978億ドルとなり、昨年1年間の864億ドルをすでに上回ったが、減税分を賄うには、留保している関税を実施するなど関税策を強める必要がある。
関税収入を減税の原資にできれば、財政的には問題ない、というわけにはいかない。米国は貿易赤字とともに財政赤字も抱えているからだ。「大きく美しい法案」は、議会予算局によると、政府の債務を10年間で2兆4000億ドル増加させるという。巨額の政府債務を抱える日本の政府が「税収の上振れ」を国民に給付する、というのと同じような構図だ。
財政赤字が膨らめば、国債を大量に発行することになるから、金利が上昇するのは確実で、その結果、景気が悪くなるのも確実だ。
利子率が成長率を上回るようになれば、財政収支(プライマリーバランス)も悪化する、といわれる。税収の伸びは名目の経済成長に相関するが、国債の利子率が経済成長率を上回るようになれば、財政に占める国債費の比率が高くなり財政収支は悪化するからだ。トランプ関税の影響で、こうした状況になる可能性が増している、と経済学者やエコノミストは警告していて、経済学者でもと米財務長官のラリー・サマーズ元米財務長官も「財政状況は、青信号の状態から赤信号に変化している」と発言している。
米国経済は成長するのか
世界銀行が2025年6月に発表した「世界経済見通し」によると、貿易摩擦の悪化と政策の不確実性によって、世界経済の2025年の成長率は2.3%で、2009年のリーマンショック、2020年のコロナ禍を除けば、2008年以来の低水準になると予測している。米国の成長率も、2025年は1.4%で、2024年の2.8%から減速すると予測している。
これは、トランプ関税による貿易の縮小などを見込んだ予測だが、トランプ政権は、各国との交渉で、当初よりも関税率を引き下げているので、成長率は上向く可能性もある。しかし、多くの経済予測がトランプ大統領の期待に反して、世界も米国も経済を鈍化させるとみている。
米国は世界最大の市場だから、米国への輸出が関税でハードルが高くなるのなら、生産拠点を米国に移す企業も出てくるだろう。しかし、そうした結果が貿易赤字の縮小や雇用の増加につながるのは、ある程度の期間が必要で、少なくとも短期的には、米国経済にとってプラスにはならないだろう。
「取引」カードとしての関税
カナダやメキシコに対しての25%の関税は、米国と接する両国から中国製の合成麻薬(フェンタニル)が国内に入っているのを阻止するためだと説明している。メキシコに対しては、不法移民の密入国も課税理由になっている。
米国が国境の警備を両国に求める事情は理解できるが、そうした対策を協議する前に関税を先行させるというのは、これまでのNAFTA(北米自由貿易協定、1994~2018)やその改訂版といえるUSMCA(米国・メキシコ・カナダ協定、2018~)でつくられてきた自由貿易圏を崩壊させるものになりかねない。それ以上に両国との信頼関係を壊すことになるだろう。
トランプ大統領は、地域的な自由貿易協定は米国の貿易赤字をふやすだけだと考えているし、効果的な不法移民対策や麻薬対策をカナダやメキシコに実施させるには、関税で先制パンチを浴びせてからのほうが有効だと思っているのだろう。
米調査機関のピューリサーチが2025年7月に実施したカナダ人の対米意識について調査によると、カナダ人の米国に対する好感度は34%で、2022年調査の63%から大幅に低下した。「好ましくない」とする比率も34%から64%に上昇した。
トランプ大統領のカナダを属州にするという発言が影響しているのは明らかで、米国を安全保障上の脅威と思うカナダ人も53%に達し、中国を脅威と考える17%を大きく上回った。
トランプ氏は大統領に就任する前から、「カナダは米国の51番目の州になるべきだ」との発言を繰り返し、2024年12月には、カナダのトルドー首相(当時)を「トルドー知事」とSNSに投稿して、カナダ国民の怒りを買っていた。トルドー氏が率いる与党の自由党はインフレなどから支持率が低下、2025年3月にはカーニー氏が党首、首相となり、4月には総選挙が行われた。当初は、不人気だった自由党から保守党への政権交代が確実とみられていたが、カーニー氏がトランプ攻勢を逆手に取り、トランプ政権への対抗と国民の団結を呼びかけた結果、自由党が議席を伸ばし多数党を維持する結果になった。新首相になったカーニー氏は5月に訪米、トランプ大統領と会談したが、トランプ氏はカナダが51番目の州になるべきとの持論を変えなかった。(写真は、訪米したカナダのカーニー首相と会談するトランプ大統領=米ホワイトハウスの「ギャラリー」から)

4 グローバリゼーションの終焉
冷戦後の潮流
1989年にベルリンの壁が崩れ、1991にかけてソ連が崩壊したことで、社会主義圏が自由主義圏に包み込まれる形で、市場経済が広がったのをきっかけに、グローバリゼーションの時代になった、といわれるようになった。この市場経済の広がりを経済発展に結びつけたのが中国で、産業革命を進めた19世紀の英国が「世界の工場」と呼ばれたように、中国は国内外からの投資をもとに製造業を発展させ、「世界の工場」になった。
中国がWTO(世界貿易機構)に加盟したのは2000年、米国に次ぎ世界第2位の経済大国だった日本をGDPで追い抜いたのは2010年、2024年には米国のGDPの64%の規模にまでなっている。経済規模で米国を脅かす存在になっているわけで、トランプ大統領は1期目から中国に対する関税措置を発動していた。
トランプ氏は、グローバリゼーションで得をしたのは中国で、損をしたのは米国という認識なのだろう。中国に高関税をかけたのは、米国の損を取り戻すには、中国を自分たちの貿易圏から排除するのは狙いだろう。こうした考え方は、デカップリング(切り離し)政策と呼ばれ、トランプ1.0から議論になり、それに沿った政策も行われてきた。
しかし、冷戦時代のように、自由主義貿易圏と社会主義貿易圏との棲み分けがはっきりしていた時代なら、お互いにデカップリングしながら、経済活動を進めることができたが、グローバリゼーションの時代になってから30年も経つと、米国製品のサプライチェーンに中国が深くかかわってきている。サプライチェーンから中国を切り離そうとすれば、米国ブランドの製品も完成できなくなっている。
今回のトランプ関税で米国は当初、中国に対する関税率を145%まで引き上げたが、米中協議で5月には30%まで引き下げた。米国が当初より大幅に譲歩した背景には、中国の独占状態にあるレアアースの輸出規制を中国が実施したためと見られている。レアアースは、先端技術産業に欠かせないもので、このカードがトランプ大統領との「取引」で、手ごわい切り札(トランプ)となった。
グローバリゼーション疲れ
トーマス・フリードマンが2000年に刊行した『レキサスとオリーブの木 グローバリゼーションの正体』には、途上国の村の若い女性たちがハンモックをネットで販売したところ、世界中から注文が来て村が潤ったという話が出てくる。グローバリゼーションが途上国にも恩恵をもたらす「実例」で、フリードマンはグローバリゼーションの宣教師と言われた。
しかし、その一方で、グローバリゼーションの波が世界に広がることで、途上国の環境破壊や格差を拡大しているという批判も強く、反グローバリゼーションの運動も広がった。1999年のWTO総会(シアトル)、2000年のIMF・世界銀行総会(ワシントン)などの会場外でのデモが話題になったが、こうしたデモは国際会議での年中行事になった。
グローバリゼーションは、ヒト(労働者)、モノ(商品)、カネ(資本)の国境を越えた移動が自由になることだ。その結果、途上国に先進国の資本が入り、安価な労働威力を使って製品をつくる工場が多く建てられるようになった。一方、先進国には、途上国の安い労働力が移民や難民という形で入ってくるようになり、それが拡大するにつれて、自国の労働者を守れという形でナショナリズムと結びつくようになってきた。反グローバリゼーションの理念が環境破壊や搾取に反対するリベラルなものから、次第に国を守るという保守的なものに変化してきた。
欧州各国では、移民の拡大に反対する右派政党が力を増し、ドイツでは極右とされる「ドイツのための選択肢」(AfD)が2025年2月の連邦議会選挙で第2党に躍進した。トランプ政権のバンス副大統領がAfDを支持したことが話題になったが、反移民と反グローバリゼーションは結びついて時代の大きな潮流になっている。トランプ大統領はその流れに乗っているとみることもできそうだ。
日本でも、2025年7月の参院選挙で、「日本人ファースト」や「反グローバリゼーション」を掲げる参政党が一気に議席数を延ばした。日本に住む外国人は2024年末で376万人、総人口の2.6%になっている。欧米に比べれば、外国人比率ははるかに低いが、この程度の水準でも、「日本人ファースト」が国民の心に響く言葉になっているのだろう。
ドイツのAfDの躍進したのは、ドイツ国内の「外国人」が増えたためだといわれる。少子化対策として移民を増やしたのと、シリアなどの難民を受け入れたのが増加の原因とされている。ドイツで暮らす人々の27%は移民の背景を持ち、そのうちの半数以上はドイツ国籍を持っている。
中間層の不安にどう応えるか
欧米、そして日本でも、外国人排斥につながるような政策や政治家が支持されるようになった背景には、欧米では製造業が中国などの新興経済国に移り、それぞれの国の中間層を支えていた製造業の雇用が縮小し、残された人々にも雇用不安を与えていることがあるだろう。
OECDの統計で、2004年から2024年までの20年間の製造業の雇用者数を米国、日本、ドイツで比較すると、米国と米国はそれぞれ9%減少、ドイツ(※)は3%減少している。日本の場合、労働人口が減少していることもあるが、製造業の海外移転に伴って、製造業における雇用機会が減っているのは確かだ。
※ドイツは2004年の製造業の統計がないため2005年と2024年を比較した。
製造業の場合、そこで働くブルーカラーもホワイトカラーも、それほど激しくないが、サービス業になると、業種によっても、個人によっても、収入の差は激しく、ストレスにさらされる度合いも製造業に比べれば、大きいだろう。社会全体で製造業が減少することは、社会的なストレスが高まることにもなるだろう。また、製造業でも、近年、経営者層と従業員との報酬・賃金格差が大きくなっていて、所得格差の拡大あるいは二極化は、実質面でも意識面でも中間層を縮小させることにつながっている。
トランプ政権は、関税によって製造業を米国に戻し、中間層を復活させる、というわかりやすいビジョンを国民に示したことが再選につながった。実際に、そうなるかは、トランプ関税が常態化するこれからということになる。私たちの「常識」は、物価高、成長鈍化、財政悪化、金利上昇などで、正反対の結果になるとみるが、トランプ大統領は、就任演説で「米国の完全な復興と常識の革命」を始めると宣言している。トランプ氏の常識と私たちの常識と、どちらが正しいのかの社会的な実験は、始まったばかりだ。
しかし、たとえ、トランプ氏の常識が間違っていた場合でも、それなら、中間層の没落をどう防ぎ、立て直すのか、という問題に新しい処方箋を示す必要がある。
中間層の没落は、日本を含め先進国に共通する課題だとすれば、その処方箋の多くは、日本や欧州各国にも通用するものでなければならない。
試金石となる日製のUSスティール買収
その試金石となるのが日本製鉄によるUSスチール(USS)の買収だ。2022年に日鉄はUSS買収で合意したが、大統領選の期間中にトランプ氏が買収に反対を表明したことから、買収は難航したが、最終的には、大統領が拒否権を持つ「ゴールデン株」を取得することで、2025年6月に日製による買収が認められた。(写真はUSSを訪問し、日鉄との提携を歓迎との演説をするトランプ大統領=米ホワイトハウスの「ギャラリー」から)

日鉄の買収へのトランプ氏の介入は、「取引」が好きなトランプ流を発揮したともいえるが、トランプ氏の狙いは、日本製鉄からできるだけ多額の新規投資を引き出すことにあったのだろう。国際競争力では劣位にあるUSSの競争力を日鉄による新規投資で優位にすることができれば、株式をだれが持つかはこだわらないということだろう。トランプ氏にすれば、名を捨て実を取ったことになる。
しかし、製鉄業は、労働集約的な産業であり、最新鋭の製鉄所を建設したところで、米国の高賃金は、国際競争をするうえで、大きなハンディになるだろう。当面、米国が鉄鋼に50%の関税をかけることで、国内市場はある程度守れるかもしれないが、鉄鋼の大きな需要は、経済成長の大きい途上国にあり、国際市場での競争でUSSが勝てなければ、買収は失敗に帰すことになる。
米ウェスティングハウスの原子力部門だったウェスティングハウス・エレクトリック(WEC)を吸収した東芝が、東日本大震災以降の原子力発電設備の高騰や縮小によって、WECが2017年に米破産法を申請、東芝も巨額の損失を書開けたことで、文字通り屋台骨が崩れたことを忘れるわけにはいかない。
(冒頭の写真は、「一つの大きく美しい法案」の成立で演説するトランプ大統領=米ホワイトハウスの「ギャラリー」から)
| 前の記事へ | 次の記事へ |



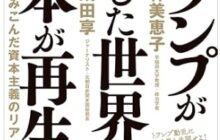
コメントする