現場に肉薄する覚悟を失ったメディアの惨状

朝のラジオニュースで、鹿児島県の霧島市に大雨特別警報が出されたことを知った。線状降水帯が発生し、8月7日夕から8日朝までの12時間で495ミリの雨量を観測したという。495ミリの雨量とは、あたり一面に50センチ近い雨が降り注いだことを意味する。
気象庁が「災害がすでに発生している可能性が極めて高い」と警鐘を鳴らしたのは当然のことで、災害報道に力を入れるNHKも、7時のニュースのトップでこの大雨特別警報のことを伝えた。これまた、当然の扱いだろう。
ところが、である。NHKが「現場からの報告」として伝えたのは鹿児島市内にある放送局の前からの記者のレポートだった。鹿児島市には大雨の特別警報は出ていない。放送時には雨もほとんど降っていなかった。トンチンカンな「現場からの報告」に唖然とした。
誰も霧島市内に行っていないのである。記者は「霧島市に通じる道路では落石や土砂崩れが発生しており、交通が規制されています」と伝えていた。ならば、せめて「行けるところまで行ってみました。通行はこのように規制されています」という映像があってもよさそうなのに、そうしたものすら放送されなかった。
霧島市は、大昔から火山活動が活発だった霧島連峰の南に広がる。火山灰などの噴出物が分厚く降り積もっており、地盤はきわめて軟弱だ。気象庁の指摘を待つまでもなく、すでに河川の氾濫や土砂崩れが各地で発生していると考えられるのに、NHKは何の情報もキャッチできていなかった。
「霧島市内に住む人が被災の様子をスマホで撮影しているはず」と考え、チャンネルを民放に切り替えたところ、テレビ朝日が系列の地元局に視聴者から寄せられた動画を流していた。川が濁流となって家屋の土台を削っており、乗用車が流されていた。こうした被害が続発しており、霧島市役所なども混乱状態にある、と考えるのが自然だろう。
近年、事件や事故が起きると、記者がよく「私は安全なところからお伝えしています」と口にする。そんなことは映像を見れば分かるのに、必ずと言っていいほど付け加える。メディアとして、組織のコンプライアンス(法令遵守)にのっとって行動していることをアピールしたいのだろう。
もちろん、記者の命と健康も大事だ。会社として取材のルールを定めて動くのは当然のことである。1991年には雲仙岳の大火砕流で報道関係者を中心に43人が死亡・行方不明になる惨事があった。命をかけてまで取材することを求めるわけにはいかない。
だが、報道する者には可能な限り現場に肉薄し、自分の目で見たもの、知り得たことを伝える使命もある。リスクがあるからと言って近づかなければ、報道の使命を十分に果たすことはできない。要は、記者の命と健康を守ることと報道の使命の妥協点を探る努力を常に続けなければならない、ということだろう。
そうした努力がおざなりになり、メディアに「現場に肉薄する覚悟」が薄れてきたのは何時からか。私は、2011年の東日本大震災が転機だったと考えている。この時、福島原発の爆発事故と放射能の大量流出を受けて、政府は原発から半径30キロ圏内に立ち入らないよう規制した。
報道機関はこれにどう対処したか。東京の主な新聞とテレビの幹部が集まり、各社とも30キロ圏から記者やカメラマンを引き揚げ、立ち入らないことを決めた。その時、30キロ圏内には畜産農家や介護施設の入所者らがまだ多数残っていた。が、彼らの生活や苦悩を取材することを放棄したのである。
放射線量を考慮し、防護服を付けての短時間の取材なら命にかかわることは避けられたにもかかわらず、各社は談合して「原稿より健康が大事」と決め込んだ。そして、みんなでその取り決めを守った。「それはおかしい」と唱え、会社の指示にあらがった者はほとんどいなかった。
この取り決めは、その後の戦争報道や災害取材にも陰に陽に影響を及ぼした。記者とて危ないことはしたくない。会社の幹部も、無理をさせて責任を問われるようなことは避けたい。こうして、「命と使命の妥協点」をさぐる作業はズルズルと命の方に傾き、使命は少しずつ遠ざかっていった。
かくして、台風を取材するのにホテルの部屋からカメラを回し、「安全なところからお伝えしています」とうそぶく記者が登場するに至った。強い風を頬に受け、たたきつける雨に打たれることもない台風取材。それを「おかしい」とも思わないメディア。報道する者がその矜持を失った時、そのツケを払わせられるのは読者であり、視聴者であり、ひいては私たちの社会そのものである。
長岡 昇:NPO「ブナの森」代表
≪写真説明&Source≫
霧島市を襲った線状降水帯(Yahoo ニュースのサイトから)
https://news.yahoo.co.jp/articles/af7666a304b470fc56d115392e185f7b3ee1bb8e
この記事のコメント
コメントする
| 前の記事へ | 次の記事へ |
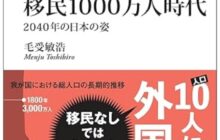


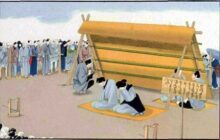
政治屋に対するジャーナリスト達の挑戦も随分減った様に思えます。私もこの国の為に何かしようとする気持ちが薄れています。そうさせるのが自民党の政治屋の戦略なら大したもの。少なからず米国の意図が働いていると思いますが。