神津多可思著『「経済大国」から降りる』を読む
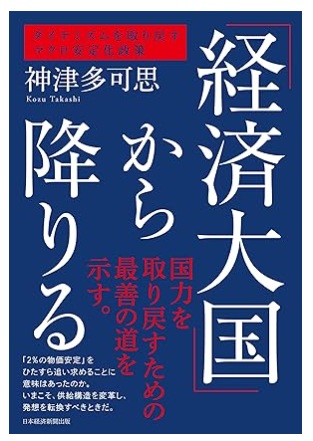
スーパーマーケットに行けば、お米だけではなく物価全体が上がっていることは明らで、「2%の物価上昇」という政府・日銀の目標には、とっくに達していると思われます。総理府が発表した2025年2月の消費者物価指数は、総合で前年同月比3.7%、」物価変動が激しい生鮮食品を除いた指数で3.0%でした。
しかし、日本銀行は「基調的な物価上昇率は2%にいたっていない」として、「基調的」という修飾語で2%目標は未達だと言い、石破首相にいたっては「デフレではないが、脱却はできていない」と、禅問答のような答弁を国会でしています。
日本経済は「デフレ」から抜け出しているのに、政府・日銀は「デフレ」という言葉の呪縛から抜け出せずにもがいているように見えます。そんな日本経済を取り巻く現状や金融財政政策の内側がわかるのが、神津多可思さんの近著『「経済大国」から降りる―ダイナミズムを取り戻すマクロ安定化政策』です。神津さんは、日銀で金融機構局審議役などに就いたのちリコー経済社会研究所主席研究員となり、現在は日本証券アナリスト協会専務理事を務めるエコノミストです。
◆2%のインフレ目標は正しかったのか
本書の副題に書かれている「マクロ安定化政策」は、急激な経済変動を避けるための金融政策や財政政策のことです。景気が過熱しそうなら、金利の引き上げや増税などの金融財政政策でブレーキをかけ、景気が落ち込みそうなら、利下げや減税などの政策でアクセルを踏み、経済を「安定化」させるのです。これは、中央銀行や政府の基本的な役割だと教科書には書かれています。
ところが、1990年代に日本で起きた「バブルの崩壊」以降の30年に及ぶ金融財政政策は、アクセルの踏みっぱなしという状態でした。とくに安倍首相(任期2012~2020年)が進めた経済政策(アベノミクス)は、「大胆な金融緩和」を打ち出し、黒田日銀総裁(任期2013~2023年)の指揮下、「2%インフレ」という目標達成のため「異次元」の金融緩和に走りました。
その結果は、どうだったのか。本書は、株価の上昇や円安の進行とともに、景気は拡大局面に入り、企業の景況感も、「バブル生成期以前の景気拡大局面と比べ遜色のない水準まで回復」とする一方で、エネルギー価格や携帯電話通信料の低下もあって2%のインフレ目標は達成されなかったとしています。このため、景気が拡大する局面になっても、金融緩和が強化され、「マクロ安定化政策としての金融政策の運営には、まったくなっていなかった」と評しています。
そもそも、なぜ、「2%インフレ」の達成に、安倍政権と黒田日銀はこだわったのでしょうか。1%程度では、日本経済がバブル崩壊以降に苦しんできたマイルドなデフレに陥る危険性がある、3%では、インフレ経済になってしまう、といった判断があったのでしょうが、本書は次のように推察しています。
「元々、是が非にもすぐに実現しなければならない水準ではなく、しかしインフレ期待を安定させるため上では、中央銀行として常に意識していたいという水準なのではないか」(p140)
◆デフレの本質は日本経済への「不振感」
そして、本書が指摘しているのは、デフレが解消され2%程度のインフレになれば、2%程度の成長が可能だという「暗黙の理解」です。これが異次元の金融緩和の背景にあったのではないか、というのです。本書によると、消費者物価と実質経済成長との相関関係は明確ではなく、2%インフレなら2%成長という暗黙の理解が「誤謬」ということになります。
高度成長時代(1955~1973)を過ごしてきた私たち世代の感覚からすると、1992年以降の1%前後の成長は、「失われた30年」ということになり、せめて2%成長ぐらいはという願望になります。しかし、本書によると、1980年代には4%程度だった日本の潜在成長率は、最近は1%程度あるいはそれ以下に低下しています。つまり2%成長ぐらいはというのが過剰期待なのです。
その原因は、人口動態の変化(1990年代後半から生産年齢人口が減少)、生産拠点の海外移転(1980年代以降の円高が背景)、非正規雇用の増大(小泉政権の規制緩和)などで、日本経済の基盤が変わったことです。
バブル崩壊で日本経済に重くのしかかった不良債権問題は、金融現象としてのデフレでしたが、2000年代の半ばには不良債権問題はほぼ解消し、「デフレ」は金融現象ではなく日本経済に対する「不振感」だったと、本書は診断しています。
こうした指摘で思い出すのは、アベノミクスの指南役だった経済学者の浜田宏一さんが「デフレは金融現象だから、マネーの供給をふやせばデフレはすぐ解消する」と、大胆な金融緩和を支持していたのが、目標だった2年を過ぎてもデフレが解消しないことが明らかになると、「日本のデフレは金融現象ばかりではなかった」と、あっさり認めたことです。
浜田さんは、デフレの「正体」は人口減少だと論じたエコノミストの藻谷浩介さんの『デフレの正体―経済は人口の波で動く』(2010年)を批判していたのですが、結果を見ると、金融現象の株価や為替は、金融緩和に反応したのですが、金融現象であるはずの物価上昇率は、期待通りに反応せず、人口動態などによる経済成長の基盤に影響されたのです。浜田vs藻谷は、藻谷さんの優勢勝ちということになります。
◆「ゾンビ企業」を生かした罪
日本経済に対する「不振感」だったデフレをマネー供給の不足だとして、国債の購入によって量的な緩和を続けた日銀の金融政策は、日本の金利体系をゆがめ、政府債務の膨張を助けました。本書は、それだけでなく、競争力が市場から倒産や廃業で退場すべき「ゾンビ」企業を生きながらえさせることになり、それが産業転換を促す経済のダイナミズムを奪った、と指摘しています。
競争力の弱い企業を金融緩和で助けたことにより、日本では欧米に比べて深刻な失業問題は発生しなかったものの、製造業主体から情報技術主体に先進国の経済環境が変化するなかで、「欧米先進国では日本ほど経済成長は停滞しなかった」と、本書は指摘しています。過度の金融緩和が経済成長を促すどころか、逆に低下につながったということになります。
米国経済を振り返ると、1980年代には、加工型の製造業を中心に国際競争力を失い、日本などとの激しい「貿易摩擦」を起こしましたが、日本のような「デフレ」に陥ることはありませんでした。本書は次にように述べています。
「米国では、情報通信技術の飛躍的な発展を具体的なビジネスに結び付け、雇用を生み収益を上げる新しい企業が次々に出た。グローバル化を通じた産業ごとの有利・不利、すなわち比較優位の変化を受け入れたうえで、産業構造を変えていったのである」(P41)
自動車や鉄鋼などの製造業の競争力は衰えましたが、IT産業の躍進という産業構造の変化が起きたというわけです。まさに産業のダイナミズムですが、そうなると、トランプ政権になった米国は大丈夫だろうかと考えてしまいます。
というのも「比較優位」というのは、それぞれの国が得意な財を生産し、それを相互に貿易することがそれぞれにとってもっとも効率的な経済を享受できる、という経済原則です。近代経済学の父といわれるデヴィッド・リカード(1772~1823)が提唱して以来の自由貿易の原則です。トランプ政権がいま進めている関税戦争は、この比較優位の原則とは真逆の保護主義ですから、経済的にはマイナスになるはずです。
トランプ政権は1期目から中国をライバル国とみなして、中国製品の輸入を制限する政策をとり、中国を米国経済から切り離すデカップリング政策だと言われました。しかし、中国以外の多くの国とは自由貿易の原則に立っていましたから、保護主義とは異なると思われていました。
ところが2期目のトランプ政権は、中国に限らず、米国の同盟国や友好国に対しても関税を引き上げて、自国の産業を守るという関税戦争を仕掛けています。これでは、比較優位を受け入れて産業構造を変化させてきた米国経済のダイナミズムを殺すことになりかねません。
◆膨大な財政赤字のリスク
本書は、成長志向に根差した「デフレからの脱却」が金融政策とともに財政政策をゆがめたとしています。不況時も好況時も財政出動を緩めないことで、国債の発行残高は先進国で最悪のレベルになりましたが、これでは大震災のような緊急事態が起きたときに財政面での対応ができない、というのです。
東日本大震災では、震災後10年間に計上した復興予算は約45兆円で、直接の被害額の約2.6倍になりました。本書は、これを想定される南海トラフの巨大地震や首都圏直下型地震にあてはめると、南海トラフでは266兆円、首都圏直下では124兆円になる計算だとしています。
これだけの資金調達が必要となれば、日本国債の格付けが投資不適格のレベルまで引き下げられる可能性があり、金利の急騰(国際価格の暴落)は必至です。そうした事態を避けるには、累積の財政赤字を減らしていくことが必要だと、本書は指摘します。国家財政の持続性が担保できないと、どんなことになるのか、本書は次のようなイメージを描いています。
「国際通貨基金(IMF)によるマクロ経済の管理なのか。不足する国家歳入を補填してくれる第三国への従属なのか。あるいは、戦後の日本のように、短時間で大きな物価水準の調整があって、物価高騰や金利の大幅上昇に伴う資産価値の減少で家計が苦しむということなのか。財政が破綻した場合の社会とは、そのようなイメージであろう」(p193)
このように列挙されると、「短時間で大きな物価水準の調整」がいちばんありそうで、別の言葉で言えば、南米で見られるような「ハイパーインフレ」になるような気がします。戦後の日本の家庭では、お国のためだと言われて買った国債が暴落して、ただの紙切れとなったときに、多くの国民は「戦争に負けたのだから」とあきらめました。南海トラフや首都圏直下型地震で、ハイパーインフレになった場合、「震災だから」と国民はあきらめるのでしょうか。
◆「経済大国」を下りる
バブル崩壊後の経済回復を求めた金融政策と財政政策が大きなひずみをもたらしているとすれば、これからの金融財政政策は、ひずみを是正して、「マクロ安定化政策」が機動的に行えるようにしなければなりません。本書はそう説くとともに、そのためには、「経済大国」から下りる覚悟が必要だとして、次のように述べています。
「日本の経済、社会はスケール・ダウンの時を迎えている。もはや『経済大国』を追うフェーズは過ぎ、それを越えて日本の国土で暮らす人々の幸福感、well-beingを重視するところに来ているのではないだろうか」(p247)
ドルベースのGDPでドイツに抜かれ世界第4位の経済国となり、国民1人当たりのGDPではG7で最下位、世界では34位になった日本の現状について、もはや「経済大国」だと胸を張る人は少なくなったと思います。とくに若い世代は、日本はとっくの昔に「経済大国」を下りているのでは、と思うでしょう。
量(経済大国)から質(暮らしやすさ)への転換が必要ということで、そのカギは、IT革命やAI革命を生かした新しい産業社会への転換を進めることだと私は思います。そのための必要条件は、産業や経済のダイナミズムを取り戻す「マクロ安定化政策」ということになります。日本の成長産業は特殊詐欺ではないか、と思われる閉塞感からは何とかして脱したいものです。
経済の関連記事
| 前の記事へ | 次の記事へ |
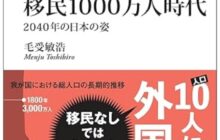

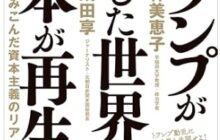

コメントする