「ならずもの国家」が跋扈する時代

パレスチナのガザ地区で朝日新聞の通信員として報道し続けてきたムハンマド・マンスール氏(29)が24日、イスラエル軍のミサイル攻撃を受けて死亡した。ガザ地区南部のハンユニスで家族と暮らしながら取材を続けていたが、避難していたテントが攻撃されたようだ。妻と子どもたちの安否は不明という。
イスラエルはイスラム組織ハマスとの停戦合意を破って、18日に攻撃を再開した。マンスール氏は死の直前、攻撃再開による惨状を伝えてきた。記事の中で、彼は「私の一日は攻撃を受けるのを避けながら、家族とともに飲料水や食料を集めることでほとんど終わってしまう」と綴っていた。
現役の記者だったころ、私もアフガニスタン戦争の取材に携わった。砲弾が飛び交う中で走り回ったこともある。取材中に死亡した顔見知りの記者もいた。だが、ガザ地区での取材は「普通の戦争取材」とはまるで異なる。自分の家族を守りながら戦争の実情を伝える――なんと過酷な取材であることか。壮絶な死、である。
国際NPO「ジャーナリスト保護委員会」(CPJ、本部・ニューヨーク)は、イスラエル軍による24日の攻撃でマンスール氏と衛星放送局アルジャジーラのホサム・シャバト記者(23)が死亡したことを非難し、国際的な調査をするよう要求した。CPJによれば、2024年に殉職したジャーナリストは124人に上り、この30年で最多だった。その7割はイスラエルによる殺害と断じている。
イスラエルにも言い分はあるだろう。今回の戦争の発端は、2023年10月のハマスによる奇襲攻撃である。ハマスはイスラエルの市民を無差別で殺害し、しかも女性や子ども、高齢者を含む240人もの人質を取った。「ハマスを壊滅させるまで戦う」と宣言して、イスラエルは戦争を始めた。ハマスは住民に支えられて戦うゲリラであり、戦闘員と住民を区別するのは難しい。壮絶な戦争になることは当初から予想されていた。
とはいえ、どのような戦争であろうと、守るべき「ルール」はある。戦闘と無関係な市民を攻撃してはいけない。投降した捕虜を殺してはならない。病院や学校などの施設を攻撃することは避けなければならない。各国は数多くの戦争を経て、そうしたことを「ジュネーブ諸条約及び追加議定書」としてまとめ、これを守ろうとしてきた。イスラエルも「ジュネーブ諸条約」を締結、批准している。
「ハマスはテロ組織である。条約など気にしていない。ならば、我々も気にしない」と言うなら、イスラエルはもはや「まともな国家」とは言えない。国際的な取り決めを歯牙にもかけない国家を「ならずもの国家」と呼ぶなら、イスラエルももはや「ならずもの国家」の一つと言うしかない。
「ならずもの国家 Rogue state 」という言葉を初めて使ったのは1994年、アメリカのクリントン大統領である。イラクやイラン、北朝鮮、リビアなどを指して使ったものだが、ガザ地区で市民への無差別攻撃を続けるイスラエルを「全面的に支持、支援するアメリカ」は、今や「ならずもの国家」のお友達と言うべきだろう。
ウクライナに侵攻し、住民を虐殺したロシアは「ならずもの国家の典型」である。そのロシアとアメリカは、国連安保理の常任理事国として「拒否権」を持ち、特別な地位にある。プーチン大統領とトランプ大統領の振る舞いは「われわれは国際社会の顔役なのだ」と言わんばかりである。2人でウクライナ戦争の始末を付けるのだという。
「ならずもの国家」とその友達がわが物顔で跋扈(ばっこ)する、恐ろしい世の中になった。そこから抜け出す道がまるで見えてこないことが一層恐ろしい。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
≪写真≫
◎ムハンマド・マンスール氏(テレビ朝日のサイトから)
https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/900021301.html
≪参考記事&サイト≫
◎ムハンマド・マンスール氏の記事と彼の死を伝える朝日新聞の記事(2025年3月25日付、3月26日付)
◎NPO「ジャーナリスト保護委員会」のイスラエル非難声明(英語)
https://cpj.org
◎ジュネーブ諸条約及び追加議定書について(日本外務省の公式サイト)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/k_jindo/giteisho.html
◎ジュネーブ諸条約の主な内容(同)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/k_jindo/naiyo.html
| 前の記事へ | 次の記事へ |
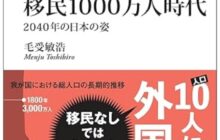



コメントする