「渡し」にはドラマがあった

けさ(2月16日)の朝日新聞オピニオン面「声」欄に「66年前の一通の投書が縁 本出版」という松田昌幸さんの投書が掲載されています。全文は下記の通りですが、文中にある「ウーラント同“窓”会」は、私も会員としてかかわっているので、この詩をめぐる話を書こうと思います。

「渡し」の詩、覚えていますか
無職 松田昌幸 (東京都 85)
1956年9月の声欄に掲載された「老来五十年 まぶたの詩」という投書がきっかけとなり、「『渡し』にはドラマがあった」という本が最近、出版された。投書は、次のような詩の出典を尋ねる内容だった。
――ひとりの老人がある川の渡し船に乗り、船頭に多めの渡し賃を払う。驚く船頭に老人は言う。「それだけ取っておいてください。お前さんには1人としか見えなかっただろうが、私は連れと一緒だったつもりだから」。老人は若かりし頃、亡き友人らと渡し船に乗ったことがあったのだ――。
当時、すぐさま反響があり、ドイツの詩人ルートヴィッヒ・ウーラントの19世紀の作品「渡し場」で、日本に紹介したのは新渡戸稲造。歌曲になっていたこともわかった。その後も関連投書がいくつか掲載され、それが縁で、「ウーラント同“窓”会」もできた。その交流の成果としてまとまったのが今回の本。平均年齢80歳超のメンバーの一人として、声欄に感謝したい。
(朝日新聞2022年2月16日オピニオン面「声」)
「渡し」との出会い
ここに登場するドイツロマン派の詩人、ルートヴィヒ・ウーラント(1787~1862)の「渡し場」(Auf Dir Überfahrt)に私が出会ったのは2006年5月に東京で開かれた「第18回カール・レーヴェ全歌曲連続演奏会」のことでした。この音楽会は、ドイツの作曲家、カール・レーヴェ(1796~1869)の歌曲を日本の声楽家たちが歌う連続コンサートで、主宰は声楽家の佐藤征一郎さんでした。
ドイツ歌曲で思い浮かぶのはシューベルトの「冬の旅」くらいという私がこの会場にいたのは、私の妻が参加している地域のコーラスグループを指導している声楽家がこの演奏会に出演していたからで、妻に同伴してコンサートを楽しんでいたわけです。
この全20曲のプログラムの19曲目はウーラントが作詞した「渡し」(Die Überfahrt、題名は「渡し場」と異なりますが歌詞は同じ)で、佐藤征一郎さんが朗々と響くバス・バリトンで、ドラマチックに曲を歌い上げました。そのとき、湧き上がる拍手の会場から、ひとりの老人がすっと立ち上がり、佐藤さんに向かって深々と頭を下げたのです。音楽会としては、なんとも奇妙な光景でした。
当時の私は朝日新聞の論説委員で、不思議な光景を見れば取材したくなるのが新聞記者の常です。後日、佐藤さんにお目にかかり、立ち上がったのは小出健さんで、この詩の事情に詳しいのは、小出さんとともに会場に来ていた松田昌幸さんだと教えられ、早速、国分寺市にある松田さんの自宅を訪ね、近くに住む小出さんにも同席していただきました。こうして書いたのが「『渡し』にはドラマがある」という見出しの下記の記事で、朝日新聞の夕刊の「窓」という論説委員が書くコラム欄でした。

「渡し」にはドラマがある
東京の音楽会で不思議な光景を見た。ドイツ歌曲を多く作ったカール・レーベの演奏会で、声楽家の佐藤征一郎さんが「渡し」という曲を歌い終わった瞬間、客席にいた老人がすっと立ち上がり、佐藤さんに深々とおじぎをしたのだ。
かつて、この渡し船に同乗した友うち、ひとりは静かに、もうひとりは戦いの嵐のなかで死んだ。その友を偲んで、3人分の船賃を船頭に払おう。そんな歌だ。
50年前の朝日新聞に、この詩の作者を知りたいという投書が乗った。それに対して「学生時代に学んだドイツの詩人ウーラントの作品だ」と応え、私訳を添えた人がいた。客席にいた小出健さん(78)だ。
小出さんがこの歌曲を知ったのは、投書のいきさつを聞いて、この詩に興味を持った松田昌幸さん(69)からだった。松田さんはウーラントの詩が好きだったこともあり、調べるうちに、この詩がレーベによって作曲されていることを知った。松田さんが日本カール・レーベ協会の代表でもある佐藤さんに連絡をとったことで、音楽会を知り、ふたりとも出席したという。
「最初から強烈な印象の詩でした。音楽会では、あらためて亡くなった友人たちを思い出しながら聴いていたら、自然と立ち上がってしまいました」と小出さん。
「この詩を調べるうちに、いろいろな人がたちがこの詩にかかわっていることを知りました。たまたま渡しに乗り合わせた旅人たちのようでしょう」と松田さん。
「渡し」の話は尽きない。<高成田享>
(朝日新聞2006年7月6日夕刊「窓」)
猪間驥一の投書

「渡し」をめぐる取材でわかったのは、1956年9月13日の朝日新聞「声」欄に掲載された投書に始まる「渡し」をめぐる長いドラマでした。「老来五十年 まぶたの詩」という見出しの投書を送ったのは当時、中央大学の教授だった猪間驥一(いのま・きいち1896~1969)で、子どもの頃に読んだ詩の作者を教えてほしいというもので、猪間は投書のなかで、この詩への思いを次のように語っています。
私は子供のころ、これを少年雑誌か何かで読んだ。そのとき、大きくなって外国語がわかるようになったら、それを読み直そうと思った。そして一、二の外国語を学んで、この詩にめぐり会おうと心がけてきたが、それ以来五十年ついに会えないでいる。子を失い友を失うこと多く、老来、この詩のこころをひしひしと感ずることがしばしばである。これがどこの国のだれの詩か、何の本に出ているか、どなたか教えて下されば幸いである。
(朝日新聞1956年9月13日「声」)
この投書が掲載されると、約40の反応が新聞社に寄せられ、松田さんの投書にあるように、この詩がウーラントの作品で、日本に紹介したのが新渡戸稲造(1862~1933)だということがわかりました。多くの反応があったのは、「まぶたの詩」にもう一度会いたい、という猪間の思いに共感した人たちや、すでにこの「渡し」を愛吟していた人たちがいたからでしょう。
読者からの反響が大きかったせいか、朝日新聞は「『まぶたの詩』に会うの記」と題した猪間の手記を学芸蘭に掲載(1956年9月27日)し、週刊朝日も同年10月7日号で「詩 人生の『渡し場』 投書欄に咲いた心の花」と題して、投書とその反応を伝えます。それでは、「渡し場」とは、どんな詩なのか、原文はドイツ語なのですが、猪間驥一・小出健共訳の日本語訳を以下に紹介します。(下の絵は、ドイツ・シュトゥットガルト郊外のホーフェンに設置された「渡し」の案内板に掲示されたウーラントの肖像。ホーフェンは「渡し」の詩の舞台だとされている)

渡し場
作:ルートヴィッヒ・ウーラント
共訳:猪間驥一・小出健
年(とし)流れけり この川を
ひとたび越えし その日より
入り日に映(は)ゆる 岸の城
堰(せき)に乱るる 水の声
同じ小舟(おぶね)の 旅人は
二人の友と われなりき
一人はおもわ 父に似て
若きは希望(のぞみ)に 燃えたりき
一人は静けく 世にありて
静けきさまに 世をさりつ
若きは嵐の なかに生き
嵐のなかに 身を果てぬ
倖(さち)多かりし そのかみを
しのべば死の手に うばわれし
いとしき友の 亡きあとの
さびしさ胸に せまるかな
さあれ友垣(ともがき) 結(ゆ)うすべは
霊(たま)と霊との 語(かた)らいぞ
かの日の霊の 語らいに
結(むす)びしきづな 解(と)けめやも
受けよ舟人(ふなびと) 舟代(ふなしろ)を
受けよ三人(みたり)の 舟代を
二人の霊(たま)と うち連(つ)れて
ふたたび越えぬ この川を
この訳詩は、上記の週刊朝日に掲載されたものです。共訳者の小出さんは中央大学の予科を修了する時期に、ドイツ語の講師から「渡し場」の原詩と英訳のガリ刷りを「餞別」だと授業で配布されて以来、暗誦し日本語訳もつくっていました。猪間の投書を読むとすぐに、そのいきさつとともに私訳を朝日新聞に送ったところ、週刊朝日はそれに猪間が手を加えたものを「共訳」として紹介しました。小出さんがレーヴェのコンサートで、「渡し」の演奏後に立ち上がるのは、それから50年後のことです。
猪間は東大経済学部で学び、卒業後は助手として大学に残り、同学部の統計学の講座を受け持つはずでした。しかし、助教授に昇進する段階で、大内兵衛(1888~1980)らマルクス経済学派の教員の圧力で東大を追放され、統計学の講座は大内に師事していた有沢広巳(1896~1988)に奪われます。東大を追われた猪間を救ったのは、当時「東洋経済新報」の主幹だった石橋湛山(1884~1973)で、同誌で猪間による統計学の連載記事を掲載します。猪間はその後、後藤新平が設立した東京市政調査会(現・公益財団法人後藤・安田記念東京年研究所)の副参事となり、戦後、中央大学の教授に就任しました。
研究者としては不遇ともいえる猪間の業績は、近年、人口問題の研究者である和田みき子さんの論文や著書『猪間驥一評伝-日本人口問題研究の知られざるパイオニア』などによって再評価されています。しかし、還暦を迎えた当時の猪間に光が当たったのは、経済学の業績ではなく、「渡し」の詩を探す投書だったといえるかもしれません。猪間は投書の翌年、投書の話などを書いた『人生の渡し場』と題したエッセー集を出版します。
日本に紹介したのは新渡戸稲造
新渡戸稲造がウーラントの詩を最初に紹介したのは、『世渡りの道』(1912)で、詩の内容を説明したあと、「親友に対するかかる切なる情けは、自然に磨かれて四囲の人々に対しても、温かき同情を表すようになる」と書いています。友情に厚い人間になれ、という処世の教えでしょう。
新渡戸は、第一高等学校の校長を辞めた直後の1913年5月に開かれた一高キリスト教青年会の卒業予定者送別会で、この詩を独語と英語で暗唱しました。このときの卒業予定者は、後に東大総長となる矢内原忠雄(1893~1961)や第六高等学校(現・岡山大学)の教授となる山岡望(1892~1978)らで、猪間の投書を読んだ山岡は、新渡戸がこの詩を吟じたときの様子を朝日新聞に伝えました。
新渡戸は、米国やドイツへの留学経験があり、英文で著した『武士道』(1900)のなかでは、古今東西の先哲の言葉を引用して博識ぶりを示していますから、原語や英訳でウーラントの詩を吟じても驚きはありません。しかし、それでも新渡戸がどこでこの詩に接し、そらんじるまでこの詩に魅せられたのか、という興味は残ります。『「渡し」にはドラマがあった』(以下、『渡し』)のなかで、そのヒントを元商社マンで、西欧の歴史や文学に詳しい釜澤克彦さんが書いています。
釜澤さんによると、ウーラントが「渡し」を発表したのは1823年ですが、その16年後の1839年に、米国の詩人で文学者だったヘンリー・ワズワース・ロングフェロー(1807~1882)が「ハイペリオン、ロマンス」という小説を発表します。そのなかに、主人公の青年が英訳されたウーラントの「渡し」を、彼が心を寄せる女性に読み聞かせ、女性が「美しい詩」だと賛美する場面が出てきます。
新渡戸が「太平洋の懸け橋になりたい」と米国のジョンズ・ホプキンス大学に留学するのは1884年で、3年間の留学中に後に妻となるメアリーと知り合います。20代前半の新渡戸がこの小説を読んでウーラントの「渡し」を知り、ドイツ語の原詩とともに、小説のなかでも使われたサラ・オースティンの英訳詩を覚え、それを後に、一高を巣立つ若い学生に披露したのではないか…。というのは釜澤さんの考証のうえに私が勝手に描いた推理です。
カール・レーヴェの歌曲

猪間の投書によって、「渡し」は広く知られることになりましたが、この詩をウーラントと同時代のカール・レーヴェが歌曲にしていたことが日本に知られるようになったのは、それから20年近くたってからのことでした。というのも、猪間は投書でウーラントの作品だと知ったあと、この歌曲をさがし求め、1961年にドイツ・ハイデルベルグに留学した際には、地元の新聞に「渡し」の歌曲を探している、という記事を掲載してもらい、「存在しない」という回答を得ていたからです。(上の写真は、レーヴェの肖像画を載せた『カール・レーヴェのワンダーランド』のCDの表紙)
猪間は、それなら「渡し」に曲をつくろうと思い立ち、再びハイデルベルグの新聞に作曲依頼の記事を載せてもらい、実際、地元の作曲家や音楽好きの人から歌曲を贈られることになります。猪間は、その顛末を文芸春秋(1963年5月号)や「音楽の友」(1965年4月号)に寄稿、猪間にとって「渡し」の物語は完結しました。
ところが、レーヴェの歌曲がわかり、「渡し」をめぐる物語は再び動き始めます。そのきっかけになったのも朝日新聞の「声」欄でした。1973年9月の名古屋本社版の「声」に、愛知県江南市の主婦からの「渡し場」の詩をもう一度知りたいという投書が載りました。その反響をまとめた「今週の声から」という声欄の記事のなかで、ウーラントの生地であるドイツ・テュービンゲンに1年間滞在していたという大学教授が「この詩はレーヴェが作曲している」という情報が伝えられました。
また、それから2年後の1975年7月には、亡くなった戦友を思い出しながら、「渡し場」を口ずさんでいるという神奈川県鎌倉市の医師が「リリー・マクレーン」のような歌はないのだろうか、という投書を「声」に投稿します。これにも多くの反響があったようで、「声」欄は「投書を追って」という記事のなかで、いろいろな反響を紹介しているのですが、ドイツの国際放送ドイチェ・ヴェレの日本語課長からは、「渡し」はレーヴェが作曲していることがわかったので、この歌曲の音源をさがして番組を作りたい、というコメントが寄せられました。
ドイツヴェレの日本語放送は、1976年4月11日の放送で、朝日新聞の投書やウーラント、レーヴェの紹介をしたあと、アロイス・ヴィーナという東ドイツのバリトン歌手が歌う「渡し」を流します。西ベルリンの放送局が20年ほど前に採録した音源で、ベルリンに東と西を隔てる壁ができる前に、この歌手が西ベルリンの放送局を訪ね録音したもので、歌手の消息はその後途絶えている、という説明が流れました。これがおそらく、日本で最初に流れたレーヴェの「渡し」でした。このいきさつも、猪間の教え子だった丸山明好さんが「声」欄に投稿しました。
ドイチェ・ヴェレは「渡し」の音源だけでなく、1900年に絶版になっていたレーヴェの楽譜も見つけ出しました。こうした努力には頭が下がりますが、ドイツの詩や歌曲に強い関心を抱いた日本人がいることに触発され、ドイチェ・ヴェレもきっと発奮したのでしょう。文化の逆流現象です。
『渡し』に寄稿した佐藤誠一郎さんの文章を読むと、この時期、佐藤さんはヴェレのあったドイツ・ケルンの市立歌劇場の専属歌手をしていました。佐藤さんは、レーヴェの研究に没頭していたそうで、絶版になったレーヴェ全集のリプリント版も手に入れていました。のちに国際カール・レーヴェ協会の名誉会員に選ばれる佐藤さんはドイチェ・ヴェレの日本語課長とも面識があったそうで、「私に聞いてくれれば、楽譜の所在は即答できたのに」と書いています。
佐藤さんは、本のなかで、「渡し」の名演は、ドイツのバス歌手、ヨーゼフ・グラインドル(1912~1993)が第2次大戦の末期にベルリンで録音されたものだと書いています。ドイチェ・ヴェレがやっと見つけた東独の歌手による録音とは別に、世界的な歌手が大戦中に「渡し」を録音し、その音源が残されていたことになります。この音源がレコード化されたのは1980年代で、「渡し」の放送には間に合わなかったことになります。
のちにCD化されたグラインドルの「渡し」を下記URLのYoutubeで聴くことができます。釜澤さんによると、この演奏はドイツの敗色が決定的になっていた1944年12月14日のもので、連合軍による爆撃の合間に録音されたのではないかとのこと。グラインドルは、ゲッベルス宣伝相から「神に祝福された(天才)芸術家)」として兵役免除など特権を与えられていたそうですが、この12月に急遽作られた国民突撃隊にいつ編入されるかという状況だったようで、そういう背景を知ると、悲壮感漂うと形容したくなる演奏です。
https://www.youtube.com/watch?v=3naeqmFz838
また、ドイチェ・ヴェレが放送したヴィーナの演奏は、放送の録音から採ったものが『渡し』の執筆者のひとりである中村喜一さんが作成している「按針亭」と題したウェブページで聴くことができます。「按針亭」の「友を思う詩!渡し場」と題したページは、「渡し」の物語が詳述されています。
https://uhland.anjintei.jp/uh2-00-watasi-gakufu-tabiji.html
ドイチェ・ヴェレの放送から30年後の2006年、レーヴェの歌曲「渡し」が日本の舞台で初演奏されました。若き日に「渡し場」の詩を覚えた小出さんが会場で感極まって立ち上がったのも、わかる気がします。
ウーラント同“窓”会
私が書いた「窓」は多くの反響があり、京都大学名誉教授の志田忠正さんや東京大学名誉教授の朽津耕三さんは、わざわざ朝日新聞社に来訪されました。「窓」の記事には、新渡戸稲造の話や猪間投書の話が書かれていないので、それを知らせに来られたのです。私は松田さんから新渡戸や猪間などの資料のコピーをいただいていたので、ファイルいっぱいの資料をお見せしたら、「小さな記事でも、記者はいろいろなデータを集めているのですね」と、ほめられたのを覚えています。「たまたまです」とは言いそびれました。
そんな話を重ねるうちに、「渡し場」に思いを寄せる人たちが集まろうということになり、ウーラント同“窓”会が発足しました。会の名前は松田さんの発案で、「窓」というコラムが縁になって同好の士が集まるのだから、同“窓”会というわけです。
同“窓”会は、2006年8月に都内で開いて以来、交流を重ねてきましたが、メンバーの平均年齢は80歳を超え、会員となった志田さんや朽津さんが亡くなりました。そこで、これまでの「渡し場」と「渡し」をめぐるウーラントやレーヴェの話をまとめて書物として後世に残そうということになったのがこの『「渡し」にはドラマがあった』ということになります。「なんとしても本にしましょう」と、後押しをしたのは、東京理科大学名誉教授の北原文雄さんで、いま102歳、メンバーの最高齢です。先日、本の出版を祝って会員有志が集まり、「志田さんや朽津さんの船賃の代わりに、私たちが献じるのはこの本ですね」という話をして、グラインドルの「渡し」を流しながら、故人に献杯をしました。
文中に名前の出てくる松田昌幸、佐藤征一郎、小出健、和田みき子、釜澤克彦、丸山明好、中村喜一、北原文雄の各氏はウーラント同“窓”会の会員です。先日の有志の会には、松田、和田、釜澤、丸山、中村の各氏のほか中山昇一氏と私も加わりました。ドイツ文学にも歌曲にも門外漢の私ですが、朝日新聞の投書や記事がこの物語の船頭役を果たしてきたので、『渡し』では、この詩をめぐる長い物語の概略を「はじめに」に書きました。
コンサートでの不思議な光景に出会わなければ私がウーラントという詩人を知ることはなかったと思いますが、音楽好きの人はシューベルトの「春の信仰」(「春の想い」)の作詞者として知っている人も多いと思います。とはいえ、ウーラント詩集の日本語訳はなく、「渡し場」の詩を所収している詩集も、三浦安子・近藤裕子共編著『詩を楽しむ』だけではないかと思います。ドイツバラードのレーヴェは、佐藤さんの尽力で、日本でもCDが販売されるようになりました。ウーラントも日本でもう少し知られる存在になってもいいような気がします。『渡し』がそのきっかけになればと期待します。
『渡し』はことし1月に仙台の出版社、荒蝦夷から出版され、一般の書店でも注文すれば定価+消費税の2420円で手に入ります。Amazonとは出版社が取引していないので入手できませんが(3338円で出品しているところがあります)、ネットでは、hontoで定価で購入できます。
https://honto.jp/netstore/search/pb_9000179814.html?tbty=0
この記事のコメント
-
新渡戸稲造については、2千円札に肖像が使われた時、親族の居た十和田市を管轄していたので、新年企画の連載を担当しました。いかにも彼が好みそうな詩で、国境を越え、言葉の壁を超えた感動の物語を知りました。有難う。
コメントする
社会 | 文化の関連記事
| 前の記事へ | 次の記事へ |

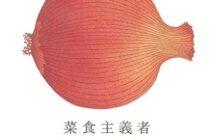


国境を越え、時代を超えて人の心を揺さぶり、語り継がれる――すごい作品ですね。語り継いだ人たちもすごい。