「裏金」の法的追及はなぜ不十分だったのか ~郷原信郎著『法が招いた政治不信』を読む~
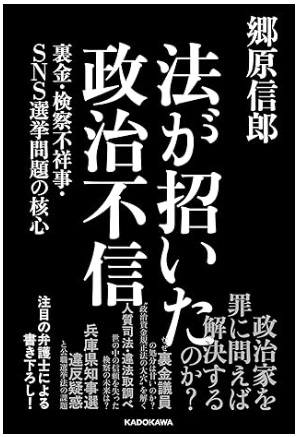
自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金問題は、岸田文雄氏から石破茂氏への首相交代や衆院選挙での自民党の大敗に直結し、政治史的には大事件になりました。しかし、法的には、清和会(安倍派)の池田佳隆、大野泰正、谷川弥一の3議員と、清和会事務局長の松本淳一郎氏ら政治団体の会計責任者や議員秘書6人が政治資金規正法(以下、規正法)の違反で起訴(略式を含む)されただけで、「大山鳴動して鼠三匹」という印象を残しました。
政治資金収支報告書(以下、報告書)への不記載が明らかになった議員は百名を超え、その総額は5年間で13億円を超えるとされたにもかかわらず、鼠級ではなく猪級の大物も含め多くの議員が法的責任を免れ、税でも課税されることがありませんでした。なぜ国民の感覚とはかけ離れた法的な対応になったのか、その疑問に答えたのが弁護士、郷原信郎さんの近著『法が招いた政治不信 裏金・検察不祥事・SNS選挙問題の核心』(KADOKAWA)です。
著者は、検察の捜査の方向性が最初から間違えたと、指摘しています。派閥の政治資金パーティーの売り上げについて、それぞれの議員へのノルマを超えた分は、派閥の政治団体(清和会など)の報告書から除外され、それぞれの議員にキックバック(還流)したのち、議員側の報告書からも除外するようになっていました。政治資金パーティーの売り上げの一部が裏金化していたわけですが、これを法的にどう処理するか、捜査した東京地検特捜部(以下、特捜)の判断が違っていたというのです。
特捜は、政治資金パーティーの還流分を政治資金として報告書に記載しなかったのは、規正法第12条(政治資金収支報告書の提出)、25条1項3号(虚偽記入)に違反しているとして、不記載の金額の大きかった池田氏らを起訴しました。しかし、著者によると、報告書の不記載・虚偽記入という犯罪成立は、特定の収支報告書に記載すべきであったことを認識していたことが要件だから、もともと報告書に記載しないのが前提の還流資金を不記載で罰することはむずかしい、と指摘します。規正法はザル法と揶揄されてきましたが、政治家個人が受領した裏金を規正法で処罰するのが難しいという状態は、「規正法というザル法の真ん中に空いた大穴」だと述べています。
素人からみると、「議員が持つ複数の政治資金団体のいずれかに記載すべきであったのに、それをしなかった」ということで立件できそうに思えます。しかし、法律の建付けはそうなっていないのでしょう。あなたは東京から名古屋までの300キロを東名高速を使って2時間で移動したのだから、時速150キロで速度違反だと追及されても、どの車を運転したのか特定できなければ道交法違反は問えない、と反論するようなものでしょうか(素人考えです)。著者は2023年に刊行した『“歪んだ法”に壊される日本 事件・事故の裏側にある「闇」』(KADOKAWA)のなかでも、規正法に大穴が空いているため、議員個人に渡されたヤミ献金が立件されなかった事例をいくつも紹介しながら、規正法での立件の難しさを指摘していました。著者は、規正法の大穴は熟知していたわけですが、特捜はこの大穴に気づかなかったのでしょうか。
検察が規正法の不記載・虚偽記入で議員らを追及した結果、派閥の資金団体(清和会など)も、還流資金を受け取った議員側も、それぞれの報告書を修正しました。しかし、修正された報告書は、収入も支出も不透明なものが多く、無理矢理に「裏」を「表」にしたのがミエミエでした。もともと報告書に記載しない、つまり議員個人が自由に使うということが前提のお金ですから、いまさら、政治活動だったことを証明しろといわれても困ったのでしょう。そんな修正を検察がよく許したなと思いますが、規正法に大穴があるため、議員側から報告書を特定してもらう必要があったのです。本書は次のように説明しています。
「議員側がどの収支報告書に記載すべきだったかを認める『自白』をすれば、起訴は可能になる。しかし、議員側が、そのような協力を行い起訴されれば罰金刑でも公民権停止となり、議員失職につながる。それを承知の上であえて検察に協力することは通常考えられない」(本書p31)
通常、考えられない危険を議員側が危険を冒して修正に応じたのは、不記載の金額による「線引き」があり、自分は大丈夫だと思ったからでしょう。資金パーティーなどの収入を報告書に記載しなかったとして2022年に略式起訴された薗浦健太郎衆院議員(当時)の不記載額が4900万円だったことから、「今回の捜査が始まった当初は『不記載額4000万円以上が立件基準』などの見方が政界で広がった」(東京新聞2024年1月20日)といいます。実際には、不記載額が3500万円だった二階堂俊博氏(元自民党幹事長)の秘書が略式起訴されたので、「線引き」は3500万円超だったことになります。
全国から検事を動員して、大規模な捜査を行ったあげく、国民が納得するには程遠い「成果」しかあげられなかったのは、規正法の大穴があったからだとすると、検察はどうすべきだったのか、検察官として長崎地検次席検事など豊富な経験を持つ著者は本書で、ちゃんと答えを用意していました。規正法の大穴を踏まえて検察捜査をするなら、規正法にある報告書の不記載・虚偽記入ではなく、規正法の「政治家個人宛の政治資金の寄付」を禁じる規定で立件すべきだった、というのです。
「収支報告書に記載しない前提の金なのだから、『政治家個人宛の寄付』であったことを授受の当事者双方に認めさせる方向で捜査を行うことは十分に可能だったはずだ」(本書p118)
派閥から政治家個人への寄付だとみなして、法的な責任を追及するとどうなるのでしょうか。報告書への不記載は、まず会計責任者が罰則適用の対象となるが、寄付の場合は秘書だけでなく議員も処罰の対象となる、と本書は説明しています。ただ、議員が対象となるのは、議員に寄付についての認識があり、犯意が認められる場合で、議員に認識がない(「秘書がやった」)場合には、法的な処罰は困難だと言います。しかし、議員の雑所得とみなすことはできるので、課税されることにはなった、というのです。「鼠三匹」よりも、裏金議員が全員、その額に応じて課税されるほうが国民の納得感は大きかったかもしれません。
「検察の捜査処分の方向性の誤りが、政治の混乱の大きな原因となった」(本書「おわりに」)という結論は、「法が招いた政治不信」というタイトルに表れています。本書を読みながら、今回の裏金事件の法的な問題がよく理解できたのは、著者の法律家としての理路整然とした語り口にあります。しかし、法律の解釈だけではなく、長崎地検の次席検事だったときに手掛けた事件などを通じての政治とカネの実態についての知識と感覚が理を裏付けているのだと思います。前掲の『“歪んだ法”に壊される日本』によると、著者は東京大学理学部卒業で、理学部では地質学鉱物学課程で学んだとあり、理論とともに実験(観察、測定、分析)を重視する姿勢を身に付けたことも影響しているのかもしれません。
今回の裏金事件で、著者は清和会所属の議員側からも取材(ヒヤリング)をしたそうで、そこで得た秘話も書かれています。それは、還流資金の流れは、もともと合法的な仕組みになっていたというのです。ノルマを超えるパーティー券収入については、清和会から党本部に寄付し、党本部から個別の議員への政策活動費として「還付」されていた、といいいます。政党から支給される政策活動費は、領収書のいらない合法的なお金ですから、議員も合法的に還流資金を使えたことになります。その後、派閥から政党への寄付という流れが省略され、派閥から議員に還流されるようになったという経緯があったそうです。たしかに、裏金が問題になったときに、多くの議員が「政策活動費のようなものという説明を派閥事務局から受けた」と述べていたのは、こうした「歴史」があったからでしょう。
著者は、裏金の追及が法的には不十分になった仕組みを丁寧に説明していますが、それだけではなく、今後へ課題も示しています。
ひとつは、いうまでもなく規正法の改正で、政治家が複数の政治資金団体を持てる仕組みをなくして、政治資金の受け入れをひとつの政治資金管理団体にしぼることを提言しています。これが実現すれば、どの政治団体の収入ということを検察が特定しなくても、報告書への不記載を立証することが可能です。
また、検察の捜査のやり方も改善が必要だとしています。現在は、ひとりの主任検事が見立てた「ストーリー」をもとに応援検事が取り調べるという方式で、著著はボートのエイト型(コックスだけが進行方向を把握している)に例えています。方向を誤らない捜査を進めるには、エイト型ではなく、個人技とチームプレーが連携するサッカー型に変えていくことが必要だと提言しています。このところ、冤罪事件が明らかになるたびに、異なる見方を主張する捜査員の主張が無視されたという話が出てきます。サッカー型に転換する時期に来ているのは明らかです。
さらに、メディアに対しても、検察のリークによる報道が被疑者の有罪視報道や過度な悪党退治への期待を招いている、と批判しています。かつで新聞記者だった私もその通りだと思いますし、先進国ではありえないような不当な取り調べや人質司法に対して、監視すべきメディアが検察からのリークを期待して批判の目をなかなか向けない、という実態もあると思います。日ごろは正義を振りかざす社会部記者が検察や警察、裁判所など司法の問題になると、口をつぐむ姿を何度も見てきたからです。
もちろん、メディアの報道によって、被疑者の人権を無視する刑事司法のあり方が改善されてきたことは認めます。しかし、そのスピードが遅く、いまだに取り調べに弁護士の同席がほとんどなかったり、保釈請求がなかなか認められなかったりする司法の後進国であるのは、「司法記者クラブ」に記者を置く大手メディアの責任が大きいと思います。
本書は、「裏金ではなく不記載」などと、事件を矮小化しようとしてきた自民党の「うそ」がわかると同時に、検察のあり方、メディアの報じ方にも私たちが目を向けなければならないことを実感させる良書になっていると思いました。
| 前の記事へ | 次の記事へ |

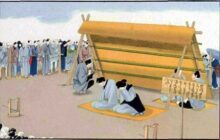


コメントする