誰もが書き、発信する時代の、エラソーじゃない“文章読本”

◇新しい時代の「文章読本」とは?
14年前に出た齋藤美奈子さんの『文章読本さん江』(2002年、ちくま書房刊)を今頃読みました。タイトルが「〇〇さん江」と“開店祝い”式です。そこから想像がつくように、大御所の各種の「文章読本」を遠慮無く批判の対 象にしています。橋本治の「えばるな、文章読本!!」をはじめとして、文章読本について論じている人たちの言も多数取り上げていて楽しめます。
文章読本というと、年配者なら谷崎潤一郎、三島由紀夫、本多勝一、丸谷才一といった大御所の本を思い出すかもしれません。齋藤さんの『文章読本さん江』の 巻末には、「文章読本」という文字通りのタイトルとは限りませんが、明治以降に出版された文章指南書をピックアップして、そのリストを参考文献として載せています。 ずいぶんたくさん出ているものです。その数約80! うち「文章読本」という言葉が入っている本は8冊でした。
齋藤さんの言いたいことは何か。齋藤さんは、権威ある大御所による文章読本の役割は終わったと断じ、インターネット時代のこれからは、コミュニケーション型の文章が主役になるだろうと予見しています。その予見に答えるかのように最近出版された本があります。私が注目する2種の文章読本は、インターネットに象徴される新しい時代が生んだ、あるいは時代が求めたものだという感を深くしています。
◇逆三角形の文章こそ
『21世紀の共感文章術』(2016年、文芸社刊)を書いた坪田知己さんの頭にあった最大の時代背景は情報の氾濫です。社会を流通する情報の量がデジタル化やインターネットの普及によって、それまでよりも桁違いに増大していることを強く意識しています。
21世紀というのは極度の情報洪水の時代であり、人に文章を読んでもらおうとすれば、まず冒頭にぐいっと引き込む文を持って来なくてはいけない。その原型は、まず結論を書く「頭でっかち」スタイルの新聞記事にあると新聞記者出身の坪田さんは言います。しかし、新聞はおもしろい文章の手本にはならないとのことで、文章指導の教室を開きながら、独自の文章論を組み立ててこられました。
ところで、音楽CDが「サビ頭」になりつつあると聞いたのは、私が今から22年前の1994年に開催していた「マルチメディア・ワークショップ」での高城剛さんの発言でした。その後、音楽はCDからネット配信の時代になって、ますます頭の出だしで聴き手を引き込むことが重要になっています。本があふれかえっている時代に、本もまさに音楽と同じように書かなくてはいけない、つまり「はじめの200字を重視せよ」というのが坪田さんの明解な主張です。
では、どうおもしろく書くか。キーワードは共感。読者にひたすらサービスする精神で共感を得よと、さまざまな切り口からシンプルかつわかりやすく、文章術のポイントが語られています。坪田さんが採用している例文がまたすばらしいのです。
著者坪田知己さんは、元日経新聞記者で、日経デジタルコアというデジタルジャーナリズムを先取りする活動に取り組んだ人です。その延長に日経電子版の誕生があります。企業が発表するプレスリリースを記事に“変換”するようなことを習い性とせず、独自視点と現場重視でやってきた坪田さんならではの本です。
◇だれでも書ける小説術
もう1冊は、私が弟(校條剛)から以前もらった本なので紹介するのは少々気が引けるのですが、(弟にはナイショですが(笑)今回はじめて読んで)たいへんおもしろかっただけでなく、齋藤美奈子さんの予見に沿った本でもあると思うので、ご紹介します。
小説家による小説の書き方本は、これまでにもいくつか出ていますが、校條剛著『スーパー編集長のシステム小説術』(2014年、ポプラ社刊)は編集者が書い小説創作法であり、しかも小説をシステムとして位置づけているところに特徴があります。つまりシステムを理解して、そこにコンテンツを流し込めば小説の一丁上がりというわけです。まあ、そんなに簡単にはいかないでしょうが、元「小説新潮」編集長としてプロ作家を相手にしてきたはずの校條剛は、「腕のいい職人になるためには、生まれながらの才能よりも、腕を磨くチャンスを増やすことが大事」であり、「ある程度の訓練期間を与えられれば小説は誰にでも書けるのです」(同書)と断言しています。
誰でも、人に読まれる文章が書ける。小説だって書ける。21世紀の文章読本はそういうメッセージを発信しています。
参考:
※『文章読本さん江』 (ちくま文庫)
※坪田知己著『21世紀の共感文章術』
※校條剛著『スーパー編集長のシステム小説術』
| 前の記事へ | 次の記事へ |
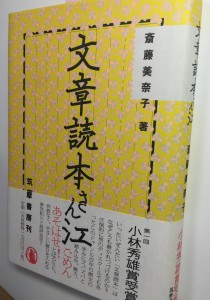




コメントする